ロッポー流「論証暗記のススメ」【司法試験・予備試験】
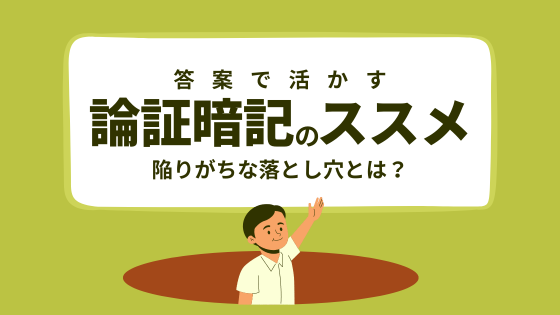
 ロッポー
ロッポーこんにちは、ロッポ―です
今日のテーマは「論証暗記」です
ぼくは内向型の司法試験合格者。凡人だけどコツコツ型。日々、静かに勉強してはプリンを作り、自転車で思索するのが好きな法律オタクです。
さて、今日のテーマは「論証暗記」。
これは、ぼく自身、予備試験の論文対策を進めるなかで何度も悩み、試行錯誤した分野です。
「論証って、暗記しないと書けないよね?」
「でも、丸暗記で本当に受かるのかな?」
そう思っていた頃の自分に伝えたいこと。それは——
論証暗記は「知識を詰め込む作業」じゃない。
「法的思考力を育てる訓練」なんだよ。
ということです。
ぼくが合格するまでに意識していた「出題の趣旨に基づいた論証暗記法」を、この記事ではじっくり解説していきます。



「出題の趣旨に基づいた論証暗記法」を解説していきますね
はじめに:論証暗記の「目的」と「出題の趣旨」
まず大前提として「論証暗記=機械的な丸覚え」では、試験には対応できません。
予備試験の出題者が見ているのは「法的思考力」と「応用力」です。
知識を使って“考える力”があるかどうかなんです。
出題の趣旨には、こんな言葉が並びます。
- 「事実関係を的確に読み取り…」
- 「正確な法的知識を前提に…」
- 「説得的に論述する能力を確認する…」
つまり、試験で問われているのは「知識」ではなく、「知識の使い方」なんですよね。論証は、その思考のベースになる“道具”に過ぎません。
だからこそ、論証は「理解し、使いこなす」ための暗記が必要なんです。



「論証」は道具ですので、使いこなしていきましょう
「論証暗記」でやってはいけない8つのNGポイントと改善策
ここからは、「論証暗記」でやってはいけない8つのNGポイントと改善策をご紹介していきます。
❶ 「理解なき丸暗記」は超危険
どこかの模範答案を写して「とにかく覚える」ってやっていたんです。そしたら、いざ事案がひねられると全く書けない…。



これ、ぼくが最初にハマった落とし穴です。
出題趣旨では「条文や判例の正確な理解」が強調されており、意味が分からないまま論証だけ覚えても、当てはめがチグハグになって評価されません。
✅ 対策
論証の規範がどの条文・判例に基づくのか、なぜそういう結論になるのかを説明できるようにしよう!
❷ 「規範と事実」を結ぶ意識が抜けている
「この規範って、どんな事案に使えるの?」
これを考えずに論証を覚えると、答案が浮いてしまいます。
出題の趣旨では、「事実に即した論述」が非常に重視されます。事実と結びつけてこそ、論証は初めて“活きる”んです。
✅ 対策
論証を覚えるときは、判例事案をセットで理解し「この結論はどんな事実が前提なのか?」を図式化して理解しよう!



論証を覚える時は、使えるように覚えていこうね


❸ 「論理構造」を理解していない
論証って、ただの言葉の羅列じゃなくて「論理の組み立て」なんです。
「AだからB、だからC」と、ちゃんと“つながってる”。
出題者が見ているのは、その一貫した論理の流れ。そこを理解しないと、ちょっと聞き方を変えられた瞬間に崩れます。
✅ 対策
論証の中で「規範」「理由付」「結論」がどうつながっているか、自分で図に描いてみよう!
❹「 キーワードと論理構造」を意識していない
覚えやすさ・再現性を高めるために、「核となるキーワード」や「論証の骨組み」はとても大事です。
そこで論証を学習する際には、以下の2点を意識しよう!
- 論証の「コアキーワード」が何かを考える
- 論証のロジックをビジュアル化する。
✅ 対策
論証をまとめる際には「キーワード」「論理のビジュアル化」を意識する。
❺ 「アウトプット」をサボっている
これはロッポ―的には大反省ポイント…。
ノートに“写すだけ”“読むだけ”では、本番で使えないんです。
✅ 対策
覚えた論証を「白紙に書く」「友人に説明する」「自分の言葉で言い換えてみる」。このプロセスを繰り返すことで、記憶が“実戦仕様”になります。



覚えた論証を本番までに“実戦仕様”にしておこう
❻ 「応用力」が足りない
予備試験では「未知の論点」が頻出します。
この場合、自らの言葉で判断基準を定立する必要があります。あるいは、判例の射程が及ぶものとして処理する方法もあるでしょう。
・問題となる条文の趣旨、利害状況を踏まえて、規範定立を行う。
✅ 対策
判例の射程を考える癖をつける



未知の論点はみんな分からない
分からない中で自らの言葉ででロジカルに論述した答案が評価されます。
❼「 最新判例・学説」のフォローがない
論証は“変化しないもの”ではありません。
学説が更新されたり、判例が変更されたりすることで、古い論証がズレることもあります。
✅ 対策
判例変更のニュースがあれば必ず判決文を一読してみよう!
❽ 自己批判的な視点がない
「この論証、本当に正しいのかな?」
「反対説って、どんなこと言ってたっけ?」
こういった問いを持つことで、論証への理解がぐっと深まります。
✅ 対策
①「判例通説」②「判例通説の理由付け」③「反対説」④「反対説の理由づけ」の4点セットでメモする習慣を!
ロッポー式「論証暗記」ステップ7
ここからは、ぼくが実践していた「論証暗記の流れ」を7ステップでご紹介します!
① 基本書と判例の精読
まずは原点に立ち返ろう。「なぜこの論証が成り立つのか」を確認!
② 論理構造のビジュアル化
頭の中で整理できないなら、書いて可視化!
③ キーワードの抽出
判断基準の核となるコアキーワードを抜き出す!
④ 暗記とアウトプット
一気に覚えず、少しずつ・繰り返す。「暗唱→記述→演習」の3段階!
⑤コンパクト論証・長文論証の検討
論証をコンパクトに論じるにはどこを削れるか。長文化するならどこを補強できるかを検討する
⑥ 定期的な復習
1週間後・2週間後・1か月後…復習スケジュールをGoogleカレンダーで管理!
⑦ 実践演習で調整
「使えるか?」を確認するのは、やっぱり答案演習。間違えてもOK!それが伸びしろ!



意外と効果的なのが「⑤コンパクト論証・長文論証の検討」だよ!
実際にやってみて欲しいな
アガルート論証集を使ったトレーニング方法は以下の記事で解説しているよ!


おわりに:論証は、知識じゃなくて“思考の型”
論証暗記というと、どうしても「暗記作業」ってイメージがあるかもしれません。
でも、本当に必要なのは“暗記された言葉”ではなく、“自分で考える力の土台”。
論証とは、法的思考を再現可能にする「思考の型」なんです。
その型を身につけることで、どんな問題でも自分の言葉で立ち向かえるようになる。
それこそが、予備試験で問われている“真の実力”なんだと思います。
ぼくも凡人で、暗記にはすごく時間がかかるタイプでした。
でも、そのぶん深く理解して、柔軟に応用できるようになっていった。
だから今、受験生のみんなにも伝えたいんです。
暗記に苦手意識があっても、大丈夫。
ロッポー
コツコツ、地道に、“考えながら覚える”。
それこそが、あなたの武器になる。
静かに、でも確実に。
ぼくら内向型は、誰にも気づかれないところで力を蓄えていこうね。



いつも応援してるよ









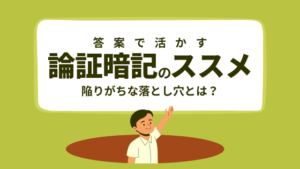
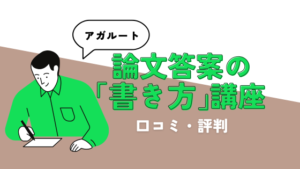

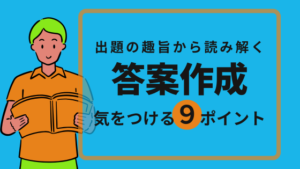
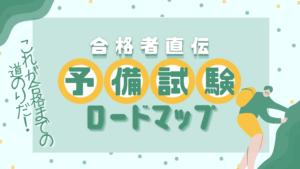


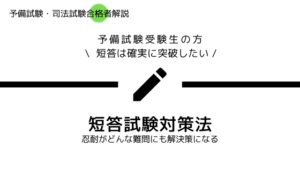



コメント