【2023年】予備試験の民法の出題傾向と具体的対策【図表あり】

「予備試験の民法の出題傾向を知りたい」
「出題傾向を基に具体的にどのような対策をすればよいか知りたい」
今回は、予備試験の民法の論文式対策について解説したいと思います。
本記事では、平成23年から最新の令和4年の出題事項を確認し、出題傾向を解説させて頂きます。
さらに、出題傾向を踏まえて、具体的にどのように予備試験の民法の対策をすればよいのかを解説させて頂きます。
まずは、予備試験の出題傾向を知るために、過去の出題事項を確認してみましょう。
なお、当サイトでは、各科目の予備試験の出題傾向及び具体的な対策を解説をしているので、よければ他の科目の対策記事も参考にされてください。
予備試験民法の出題傾向
過去の出題事項を表にまとめてみました。
予備試験民法の出題事項
| 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 |
| 請負契約の契約不適合責任 修補に代わる損害賠償請求 取得時効 | 制限種類債権の履行不能 集合動産譲渡担保と所有権留保の優劣 | 無権代理人の後見人就職 詐害行為取消権と債権者代位権 | 不動産物権の優劣 法定地上権の成否 取得時効 |
| H30 | H29 | H28 | H27 |
| 債務不履行に基づく損害賠償と不法行為に基づく損害賠償の具体的規律の相違
仮想離婚と責任財産の分与 | 実体的権利関係に合致しない登記を信頼した第三者の保護
不動産賃貸借の合意解除と転貸借関係 | 他人物売買の買主が、売主が買主に所有権を移転することができなかったことを理由に解除した場合の法律関係 | 建物の過半数の持分を有する者が、他の共有者に明渡を求めることができるか
贈与者の債務の法的性格と承継後の法律関係 |
| H26 | H25 | H24 | H23 |
| 民法634条第一項本文に基づく修補請求
民法634条第二項前段に基づく損害賠償請求 | 将来債権譲渡の効力
債権譲渡担保 | 検索の抗弁と事前求償権が、物上保証人に認められるか
遺留分減殺請求権 | 民法94条第2項の善意の第三者に関する基本的理解
他人物の売主及び賃貸人が所有者を相続した場合の法律関係 |
予備試験民法では、上記の表のとおり、民法総則から家族法まで幅広く出題されています。
平成30年は、論点が明確な問題が出題されました。論証を全て暗記していれば、対応することが容易だったでしょう。この傾向が続くのであれば、民法は得点源となる科目となります。
他方、平成29年までは、論点の抽出が難しい出題が続いていて、論証を覚えていただけでは、解答することが難しい問題でした。論点数が多い上に、難しいとなると勉強の優先順位は低くてもいいでしょう。
令和元年以降は、無権代理人の後見人就職などマイナーな論点が出題されている他は、通常の勉強で十分対応可能な論点が出題されています。
したがって、民法では典型論点に対応できるようになることが対策の方針となります。
予備試験民法の具体的対策
出題傾向がわかったところで、予備試験の民法の具体的な対策について考えていきましょう。
民法の論点を網羅
上記のとおり、予備試験民法では、各分野から満遍なく出題されているため、他の科目以上に「網羅性」を徹底することが必要となります。
まずは、既存の論点を網羅しましょう。
私が使用していたアガルートアカデミーの論証集では、270個の論点が収録されています。この270個の論証の全てを暗記しましょう。全文を覚える必要はありませんが、全ての論証について論理の流れを理解して暗記して、またキーフレーズを覚えましょう。
動機の錯誤の論点を題材に私の勉強法を説明したいと思います。
※改正前民法の「錯誤無効」制度を前提とした説明です。
まず、①から④の流れを理解して覚えます。
この流れを覚えておけば、あとは現場で、それらを言語化すればいいのです。全文を覚えるのは大変ですが、この程度なら覚えることも可能でしょう。動機の錯誤の論点くらい超重要論点であれば、ここまで覚えることもなく、論証することも可能だと思いますが、マイナー論点もこのような形で、自分のものにしてください。
次に、自分で言語化できるとしても、判例と同様の表現をすべきキーフレーズがあると思います。
動機の錯誤の論点で言えば、最高裁平成28年1月12日の「当事者の意思解釈」「法律行為の内容」はキーフレーズとして、そのまま表現した方がいいと思います。このような重要なキーフレーズは、別途暗記できるように努めましょう。
上記のような方法で、論点を網羅しましょう。
論点学習の具体的な方法は、アガルートの論証集を使ったん勉強がおすすめです。下記記事でかなり詳しく解説をしているのでよかったら合わせて確認してください。


本章を要約すると以下のとおりです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 網羅性の重要性 | 予備試験民法では各分野から満遍なく出題されているため、網羅性が必要 |
| 論点数 | 例えば、アガルートアカデミーの論証集では270個の論点が収録されている。 |
| 学習目標 | 論証集記載の全ての論証の論理の流れを理解して暗記、重要なキーフレーズを覚える |
| 学習方法 | 論証集を利用する。別途詳しく解説している記事も参照推奨 |
民法の百選掲載判例を網羅
予備試験民法は、百選掲載の判例から、出題されることも多いです。
受験生としては、上記論点の網羅に加えて、百選掲載の事案と判旨を押さえておきましょう。解説を読む必要はありませんが、「事案」と「判旨」を押さえてください。
百選掲載の判例の中には、複雑な事案も多いですが、ここでサボることなく、事案を解析することで、予備試験の事案解析も効率よくできるようになります。また、事案をしっかり理解することで、当該事案における「争点」がわかります。
「争点」を理解した上で、判旨を読むことで、この事案の何が特殊なのかということがわかります。さらに、論点を事案と結びつけておくことで、論点の抽出を素早く行うこともできるようになるでしょう。
どの科目にも共通して言えることですが、百選掲載判例の「事案」と「判旨」は、受験生の必要最低限の知識と考えてください。
よく、「判旨」だけ読む人や、論点だけ学習している人もいますが、合格レベルに達するには「事案」まで知っていること必要だと考えています。
平成28年度の動機の錯誤に関する判決って、どんな事案だっけ?と聞かれた場合に、事案の概要を説明することができるように準備しておくべきです。
上記のことは判例の射程を論じるためにも必須です。かならず「事案」と「判旨」をセットで勉強しましょう。
判例の勉強には判例集が必携です。基本的には判例百選で良いかと思いますが、下記外部サイトのおすすめの判例集の記事を参考にしながら、判例集を選んでみてください。


本章を表形式で要約すると以下のとおりです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 百選掲載判例の重要性 | 予備試験民法では百選掲載の判例から出題されることも多い |
| 学習目標 | 百選掲載の事案と判旨を押さえておく。解説は余裕があれば。 |
| 事案解析の利点 | 事案を解析することで、予備試験の事案解析も効率よくできるようになり、争点がわかり、論点の抽出を素早く行うことも可能 |
| 必要最低限の知識(合格レベルの条件) | 百選掲載判例の「事案」と「判旨」。事案と判旨をセットで勉強する。 |
| 教材 | 判例集。基本的には判例百選 |
条文を引く習慣を身に着ける
民法の条文数は、1050条です。刑法の条文数が264条であることと比較すると非常に条文数が多い法律です。それもそのはず。民法は私法の一般法であり、私法の全ての根幹となる法律です。
法的三段論法は、条文から始まります。
そのため、条文を知らないと法的三段法をすることができません。
また、上記のとおり民法の条文数は多いです。
普段の勉強から、条文を引く習慣を身につけましょう。その際にお勧めの方法は、目次を確認してから該当条文を検索する方法です。
ある程度勉強をしてくると、物権総則関係の条文はこのあたりで、賃貸借の条文は601条からだなとか覚えてくるのですが、民法の全体像と勉強しているテーマの位置づけを確認するためにも目次をみてから条文を検索するようにしてください。
昔から言われていることですが、条文を疎かにする人は伸びません。他方で、普段から愚直に条文を引いてきた人は、ぐっと伸びていきます。
したがって、制度や論点を勉強したら、その議論の前提となっている条文を確認しましょう。
事例演習を繰り返す
予備試験の民法の主題傾向からして、突飛な出題はされていません。典型論点の組み合わせをした問題が多いです。
しかし、民法は論点数が多いため、論点の抽出レベルで差がつきます。
基本問題を繰り返す学習し、勘所を押さえる必要があります。
また、事例演習をする際には、法的三段法のうちどこのステップが苦手なのかを分析してみましょう。自己分析です。どのレベルの課題があるのかを分析することで、対処法が明確になります。
たとえば、論点は抽出できるのに規範がうまく書けないのであれば、論証集を使って論点学習をするべきでしょう。他方で、あてはめが苦手なのであれば、元となる判例の事案を理解できていないため論述ができていない可能性が高いです。
このように事例演習を繰り返し、自己分析をし、具体的に対処する。これをくりかえしてください。
そして、事例問題は演習書選びが非常に重要です。特にこだわりがないのであれば、アガルートの重要問題習得講座の問題集が良いかと思います。詳しくは、以下の記事で解説をしています。
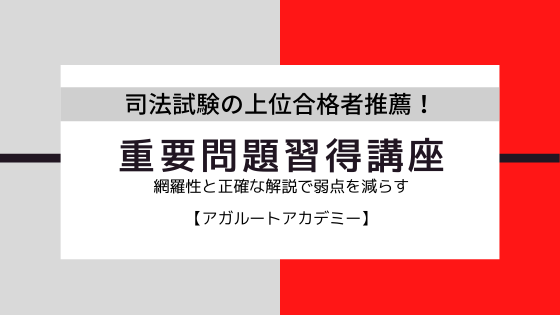
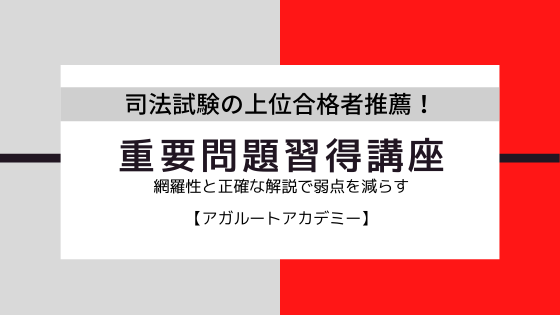
最後に
いかがでしたでしょうか。
平成23年から令和4年までの予備試験の過去問の出題傾向を踏まえて、予備試験民法の具体的な対策方法を解説させて頂きました。
「民法」はすべての法律の基本的な思考や考え方の基礎になります。民法が苦手な受験生も多いかと思いますが、対策方法は本記事でご説明させて頂いたとおりシンプルです。
「継続は力なり」です。しんどいと思いますが、少しずつ前に進んでいきましょう。
また、本記事を読まれている方は「予備試験に挑戦している受験生」かと思います。予備試験は、人生を変える試験です。合格前と合格後の人生で大きく変わります。限られた者がたどり着けるものです。そのためには、強力なサポートが必要なことがあります。
もし、この記事を読まれている方が予備校のサポートを受けたいと考えているのであれば、是非、アガルートを検討してみてください。
私は、アガルートアカデミーの講座を受講してから、司法試験の対策のメカニズムがよくわかり、結果的には予備試験に合格し、翌年の司法試験にも合格することができました。本当にアガルートの講座を受講してから見える景色が変わりました。合格する人は良い師匠や教材に出会っています。この記事を読まれている方がもし、アガルートの講座の受講を検討したことがないのであれば、下記記事を参考に検討をしてみてください。そして、受講によるメリット、デメリットをよく考えてください。
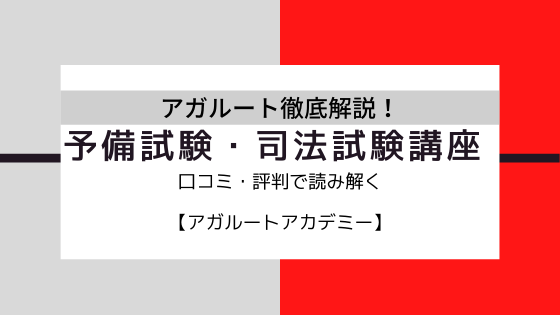
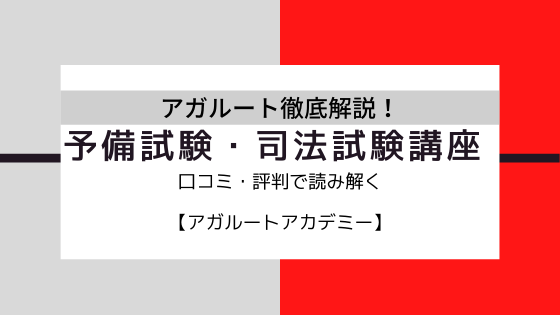
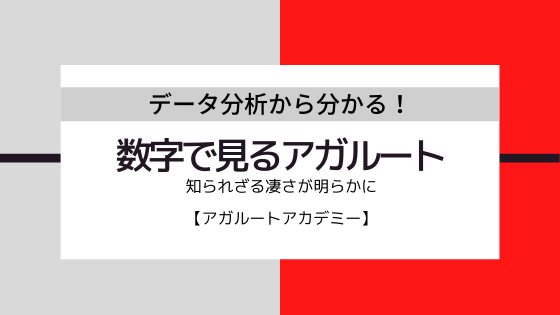
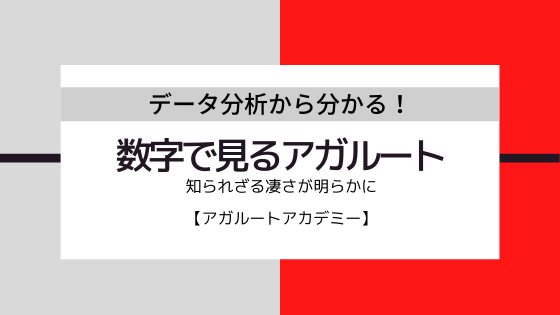
また、予備試験の勉強法についてより詳しく知りたい方は下記記事を参考にしてみてください。
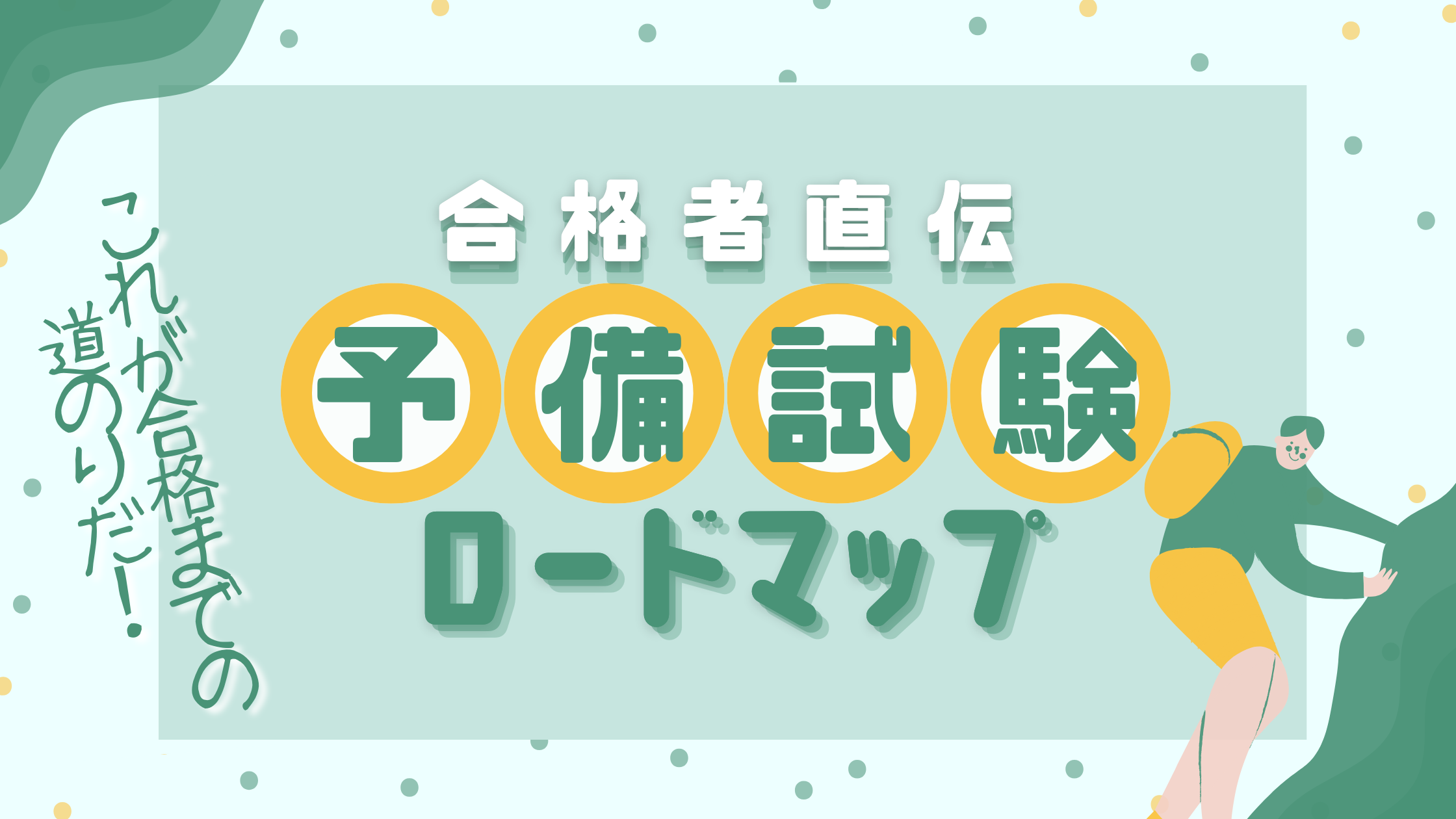
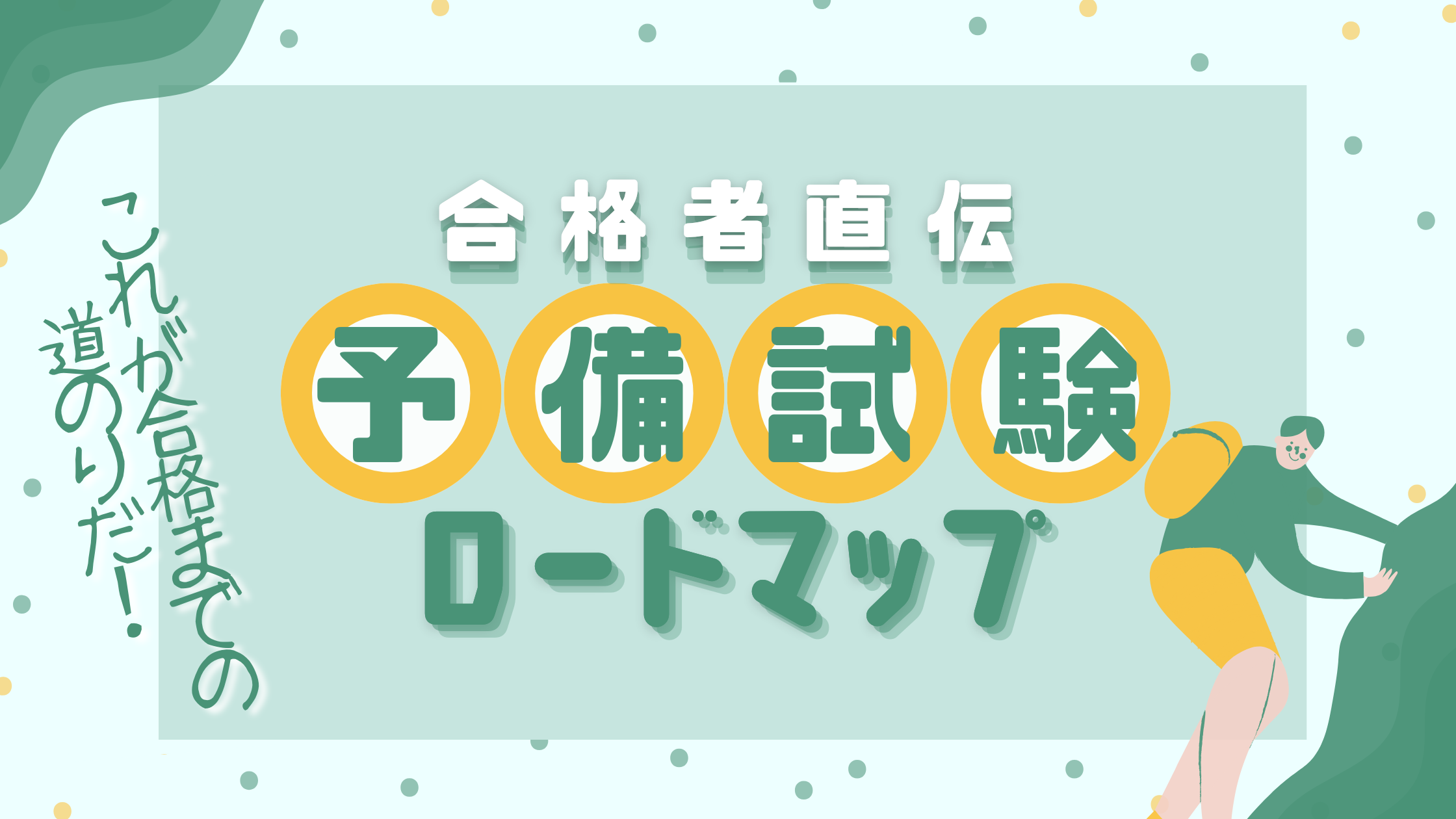












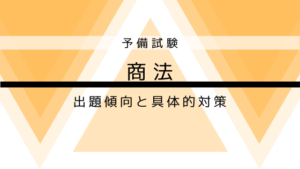

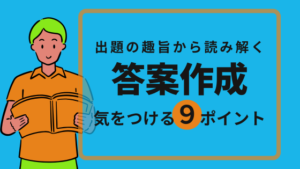
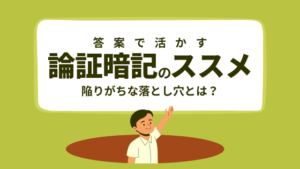
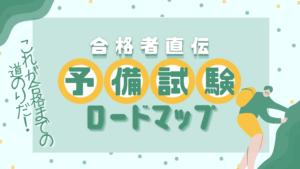

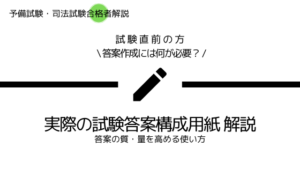

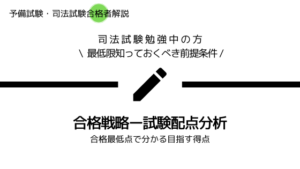

コメント
コメント一覧 (3件)
[…] あわせて読みたい 【2023年】予備試験の民法の出題傾向と具体的対策【図表あり】 […]
[…] […]
[…] 【2023年】予備試験の民法の出題傾向と具体的対策【図表あり】 […]