【2024年】司法試験の答案構成用紙の使い方【上位合格者が公開】
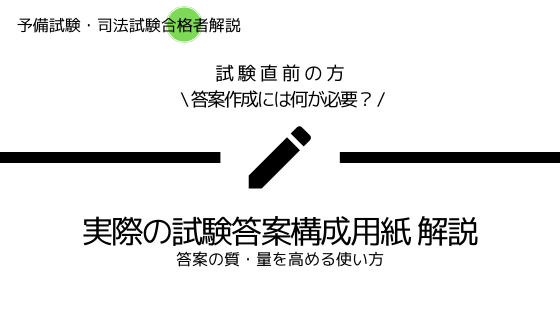
今回は、司法試験本番で使用した答案構成用紙を公開したいと思います。皆さんは、司法試験の本番で配布される答案構成用紙が、どのようなものなのか知っていますか?
司法試験本番で答案構成用紙をフルに活用するために、事前にどのような構成用紙が配られるのか知っておくべきだと思います。また、この記事では、私が令和元年司法試験でどのような答案構成をしていたのか、実際に使用した答案構成用紙を公開します。さらに、答案構成をする際に意識していた点もお伝えします。
司法試験本番でどのような答案構成用紙が配られるのかを知らない、あるいは、司法試験合格者がどのような答案構成をしていたのか知りたいという方に読んで頂きたいです。
前回は、令和元年司法試験で実際に使用した問題集を公開しました。こちらの記事をまだ読んでない方は、こちらも参考にしてください。
令和元年司法試験で実際に使用した答案構成用紙
さっそく私が令和元年の司法試験で使用した答案構成用紙を見てもらいます。こちらは、民法の試験で使用した答案構成用紙です。




答案構成用紙の枚数とサイズ
司法試験本番では、問題検討のため、答案構成用紙が各科目1枚(A3版)配布されます。令和2年司法試験に関するQ&A(法務省)でも、A3版の答案構成用紙が各科目1枚配布されることを明記しています。
司法試験の受験生は、A3の裏表を使って答案構成をすることになります(前回の記事でも説明したように、問題集にも余白があるので、その余白を活用して、答案構成をすることもできます)。司法試験受験生としては、このA3版の答案構成用紙をどのように使うのか事前にシミュレーションしていた方が良いでしょう。
私は半分に折って使っていました
問題文を読みながら答案構成を作る際に、A3版では大きすぎて使いにくかったので、私は、答案構成用紙を半分に折って使っていました。写真の答案構成用紙に折り目が入っているのはそのためです。この辺は、好みだと思いますが、私と同じように半分に折って使っていた方も多いかと思います。
答案構成で意識していたたった3つのこと
答案構成の目的は、答案の質・量を高めることにあります。そして、この目的を達成するために、答案構成では、以下の3つのことを意識するようにしていました。
1. 事案の図式化
まずは、事案の図式化です。事案分析の前提として、事案を正確に把握することは不可欠です。そして、事案を正確に把握するためには、事案をビジュアル化することが役に立ちます。最近の司法試験では、そこまで問題文が長くないですが、それでも、ビジュアル化することなく事案を正確に把握することは困難です。
また、問題文を読むだけでなく、実際に手を動かして図式することで、事案の理解が深まり、処理スピードが上がります。さらに、未知の論点を論証する際にも、この図式がヒントになって、検討の切り口を見つけることも少なくありません。以上のような理由から、原則として事案の図式化をするようにしていました。
他方、事案が複雑でなく、イメージがしやすい場合には、図式化をしないこともありました。例えば、令和元年の憲法では、写真のような図式はしていませんでした。問題に応じて、図式化をするかどうか判断されるのが良いと思います。
2. 検討の順序
答案構成には、検討の順序を記すように意識していました。写真の(1)(2)とかは、検討の順序を示しています。
これには、答案作成の際に、①書き漏らすことを防ぐ目的と、②論理性を高める目的の二つの目的があります。答案構成の段階で気づいていたことも、答案で表現できなければ意味がありません。答案構成で気づいたことも、作成に夢中になっていると忘れてしまうものです。そのため、見出しだけでも良いので、答案で書くべきことが一見して分かるようにしていました。
また、検討の順序が適切であれば、一つ一つの検討がグダっていても、全体としては一貫性のある答案になります。司法試験の本番で、不十分な論述をしてしまうことは仕方ありません。私の再現答案でも、個々の論述は、不十分であったり、言葉足らずの点が沢山あります。それでも、検討の手順を守っているため、全体としてはまとまりのある答案になっているかと思います。
以上の①②の理由から、答案構成用紙で検討の手順を記しておくと良いと思います。
3. 答案で使う事実を特定
答案構成用紙を見れば、答案で使うつもりの事実が問題文中のどこにあるのが分かるようにしていました。答案構成用紙にある蛍光ペンの色を、問題文中のマーカーと対応させていました。
「あの事実どこに書いてあったかな」と答案作成中に、問題文を何度も読み直すことがあり、この時間がもったいないと思っていました。そこで、使う事実がどこにあるのかが分かるように、答案構成の段階で、使う事実にマーカーを引いて、その色でどこでどの事実を使うのかが分かるようにしていました。




例えば、答案構成において、「設置または保存に瑕疵」の右横に、緑の蛍光ペンを引いています。そして、問題文には、「設置または保存に瑕疵」で使うべき事実に緑色マーカーが引いてあります。
こうしておくことで、答案を作成する段階で、「設置または保存に瑕疵」を論じる際には、問題文を見れば、どの事実を使うのかがすぐにわかります。ちょっとした工夫ですが結構効果あります。私の場合、このやり方をするようになって、答案作成中に問題文を読み返す時間が減りました。
ただ、必ずこのような方法で色分けしていたわけではありません。現場の判断で、マーカーをしないこともありました。例えば、上記の令和元年民法の問題であれば、問題文中に設問が挿入される形式だったので、設問で使うべき事実もそれまでの問題文にあります。
そのため、別にマーカーで色分けしなくても、ちょっと読み直せば、該当の事実を容易に見つけることが出来たと思いますし、マーカーをする分、時間ロスになっていたようにも思います。最終的には、現場の判断で、答案作成をする上で必要なのかどうかを考えて答案構成を作成することが大切だと思います。
最後に
今回は、令和元年司法試験本番で使用した答案構成用紙を公開しました。答案構成の方法をまだ確立できていない方は、是非参考にしてみてください。
【法律書籍専門の口コミサイト】











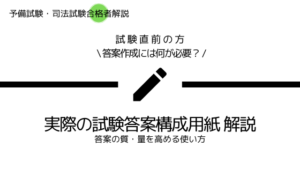
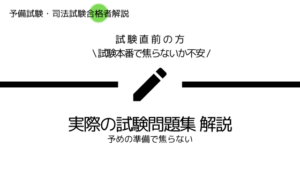
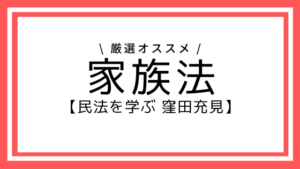
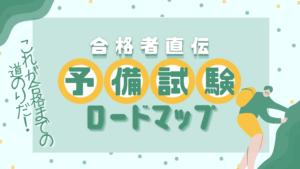


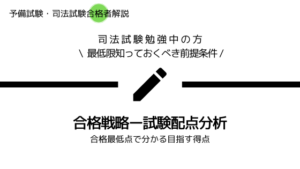
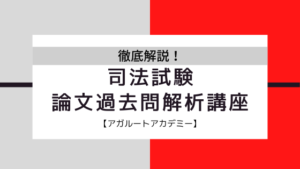
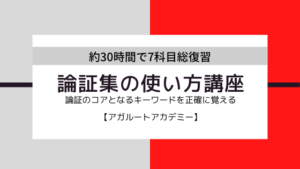
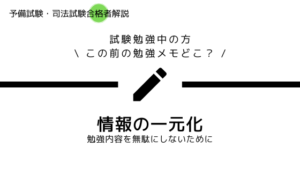
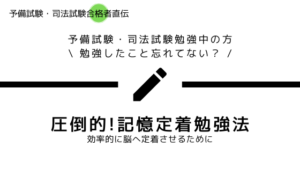

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 実際の答案構成用紙の使い方はこちらの記事をご確認ください。 […]