司法試験本番に持参した持物7選と机上に置いた物7選【準備は万端?】

『司法試験本番に持って行った方がいい物、グッズどは?』
『司法試験本番に机上に置くものは決まっていますか?』
『司法試験に持っていくものを悩んでいませんか?』
今回は、司法試験本番に持参したグッズと司法試験本試験中に机上に置いたものをご紹介したいと思います。直前になって慌てないように、何を持参するのかを余裕があるうちに決めておきましょう。
これから、「本番に持参したおすすめグッズ7選」と「本番で机上に置いた物7選」の厳選した14つのグッズをご紹介してきます。
司法試験本番に持参したおすすめグッズ7選
まず、前提ですが、住んでいるところから試験会場までが遠かったため、司法試験会場近くのビジネスホテルに宿泊しました。司法試験一日目の前日からビジネスホテルに宿泊し、朝は、ビジネスホテルから会場に向かいました。
ホテルに宿泊するか悩んでいる方もいるかと思いますが、個人的にはホテル宿泊がおすすめです。電車の遅延が怖いですし、試験に向けて集中力を上げていくためにも、満員電車に乗っていくよりかはら、歩きで迎える方が良いかなと思います。
前置きはこれくらいにして、まずは司法試験本番に持参したおすすめグッズ7選をご紹介したいと思います。
概要は以下のとおりです。
- 耳栓
- 薬(胃薬、頭痛薬)
- 目覚まし時計
- 直前見直しシート
- 論証集
- 総合講義テキスト
- スマホ、充電器
順に解説していきます。
①耳栓
ホテル宿泊者には非常におすすめです。
ホテル宿泊で怖いのは、いつもの慣れた環境ではないため寝づらい点です。ホテルが幹線道路に面していたり、たまたま隣室が騒がしいという可能性もあります。
しっかり睡眠がとれるように耳栓を持参されるのをおすすめ致します。
私は以下の耳栓を購入していました。余った分は、普段勉強する際にも使用できます。
②常備薬(胃薬、頭痛薬)
普段から飲みなれた薬も持っていきましょう。
私は、胃腸が弱く、緊張でお腹が痛くなる可能性が高かったため、持参が必須でした。
試験当日は、緊張や疲労等様々な要因で頭が痛くなる可能性も考えました。頭痛や腹痛は突然にやってきます。その時に普段飲みなれた薬があれば、すぐに対処できますので非常に便利です。
持って行かなかった場合、最近ではコンビニなどで気軽に入手可能ですが、怖いのは体に合わなかった時です。過去に私は、普段飲まない薬を飲んだ時に、恐ろしいほど体調を崩したことがあります。これが試験当日だったらと思うと恐ろしいと思いませんか?
いつでも飲めるよう、少しでも良いので薬を持っていくと良いと思います。
③目覚まし時計
目が覚めると…出発時間だった…。この状況恐ろしいと思いませんか?
体調不良も怖いですが、寝坊も恐ろしいです。
慣れないホテルで、寝つきが悪く朝起きれないなんてざらにあります。そんなときのために、目覚まし時計も持っていきました。ビジネスホテルにも当然、アラームを設定できるのですが、万が一を考え、目覚まし時計も持っていっていました。
歩いて止める必要があるほど、遠くにおいておくと安心ですね。
④直前見直しシート
これは、「令和時代の司法試験攻略法」で紹介した直前見直しシートです。ケアレスミスを防ぐためによみ見落とす事項などを整理したメモです。
主に、試験本番の休憩時間に見直していました。記憶はすぐに忘れていきますが、これがあれば、少しでも保つことができるのでお勧めです。
⑤論証集
私は、論証集に論証に関する知識を一元化していました。直前見直しシートと共に、試験本番の休憩時間に見直すために試験会場に持ち込んでいました。
私の起案力を劇的に向上させた勉強はこちら!
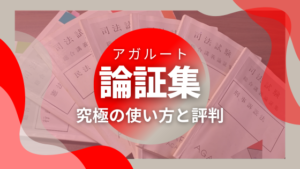
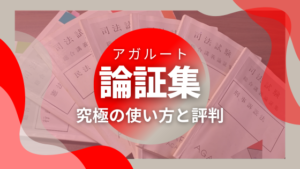
⑥総合講義テキスト
試験会場にはもっていっていないですが、ホテルには持ってきていました。私は、総合講義は司法試験当日まで使う教材と言って来ていますが、本当に当日の朝まで見直しに使っていました。
1日目が終われば、二日目の科目の総合講義を読み直していました。二日目が終われば三日目の科目の総合講義を見直していました。
一元化テキストであれば、何でも良いですが、自分がメインで使ってきた教材は、少なくともホテルには持参をした方が良いかなと思います。
なお、総合講義を全科目持っていくと結構重たいです。なので、スーツケースに入れて持っていきました。
総合講義の受講方法、一元化方法はこちら!


⑦スマホ、充電器
充電器は忘れがちですので気をつけてください。これは当然必要なものです。
不慣れな土地で会場までの地図を探すときにも、支払いをするときも、試験前に気になることもスマホがなければ不便な一日を過ごすことになります。
また、受験票をスマホで写真を撮っておくと、試験会場で座席を探す際に便利だと思います。
+羽織もの
体調を気にするうえで忘れてはいけないのは、温度管理です。
空調が何度になっているかなんて予測のつけようがないですよね。
寒すぎて身震いをしたり、手先がかじかみすぎて動かないなんてことも…。逆に熱くてボーっとしてしまい、汗も気になって…。と集中できない可能性がありますよね。そのため、意外と服装も大事です!
また、タイトな服装よりかはゆったりした服装がお勧めです。リラックスした状態で受けることができますし、長時間座りっぱなしの環境を考えるとよいでしょう!
司法試験本番で机上に置いた物
続いて、司法試験時に「机上に置いた物」をご紹介します。
以下の物を机上に置きました。
- 試験用タイマー
- 腕時計
- 0.7ボールペン4本
- 4色+シャーペンのボールペン
- 蛍光ペン5色(ノック式)
- ハンカチタオル
- 受験票
以下、簡単に理由を説明します。
① 試験用タイマー
私は、腕時計に加えて試験「専用」のタイマーを使用していました。
試験中に戦略的に問題を解くためには、残り時間を正確に把握することが不可欠です。試験に持ち込まれる時計は人それぞれです。腕時計を持参する人もいれば、置き時計やストップウォッチを使用する人もいます。
その中で、私はこの試験用タイマーを持ち込みました。司法試験や予備試験を受験したことがある方なら、見かけたことがあるかもしれません。
実際、私も予備試験の短答試験で隣の人が使用しているのを見かけて知りました。
今回は、3点に絞って本タイマーの魅力を解説したいと思います。
この記事で最も伝えたい点はこのタイマーです!
コンパクト
まず、第一にコンパクトなサイズで試験中に邪魔にならない。机を最大限活用することが出来ます。受験票に始まり、机上に置くものは意外とあります。省スペースという観点は、試験用タイマ選びのひとつのポイントと言えるでしょう。
無音モード
第2に、無音モードが搭載されています。本タイマーは、試験用に設計されたタイマーですから、試験受験者の要望に応えたものとなっています。
音の代わりに、赤い光で終了を知らせてくれます。




当たり前ですが、試験中にアラーム音を鳴らすと試験員に注意されます。
そのため、無音モードが搭載されていることは、試験用タイマーの必須要件と言えますね。
無音モードが搭載されているので、試験に安心して取り込むことが出来ます。
多機能かつ直感的な操作感
第3に、試験の必要な限度で多機能かつ直感的な操作感
無理やり一つのポイントに押し込みましたが、この点も取り上げるべき本タイマーの魅力です。
試験に必要な限度で多機能です。
タイマーモードのみならず、時計機能もあります。仮に、試験開始時にボタンを押し忘れたという場合も時計モードにチェンジすることが出来ます。
また、タイマーモードもお好みでカウントダウンまたはカウントアップを選択することが出来ます。
さらに、試験用に設計されたタイマーですので、細かな設定は不要であり、直感的に簡単に操作することが出来ます。
ストップスタートボタンは中央のみであり、早押しボタンのような感じです。
私はカウントダウンモードを利用していました!


例えば、カウントダウン及び無音モードでボタンを押すと同時にカウントダウンが始まりゼロになると赤い光で知らせてくれます。
以上が本タイマーの紹介でした。
- コンパクト→机を最大限使用できる
- 無音モード搭載→安心して試験に集中できる
- 多機能かつ直感的な操作感→各人に応じた使用ができ、直感的にわかりやすい操作が可能
②腕時計
念のため試験用タイマーとは別に腕時計を置いてました。試験開始前に、時刻は正確に合わせておきましょう。
③ 起案用ボールペン4本
愛用のペンを複数持っていきましょう。私が愛用した起案用のペンは、エナージェルユーロ0.7です。
0.7のためインクがなくなりやすい点は注意です!
速記用ボールペンとして定評があるボールペンです。ゲルから素早く液体化及び乾燥するように作られています。
現時点で、個人的にナンバーワンのボールペンです。
綜合講義100のテキストに書き込む場合は、0.35がオススメです。
こちらのボールペンに出会うまでは、万年筆も考えていたんですが、エナージェルユーロを知ってからは、これで十分であると思うようになりました。
④4色+シャーペンのボールペン
答案構成は、4色ボールペンと、蛍光ペンを使用してました。
効率的な答案構成の使い方を考えてみると面白いかもしれません!
実際の答案構成用紙の使い方はこちらの記事をご確認ください。
設問ごとに、色を変えて、重要な事実には蛍光ペンでマークして、同色のボールペンでメモ書きをするような感じで使っていました。 ただし、実際には、起案用のペンでメモ書きすることが多く、特に重要な事実を強調するために、色ペンを使っていたという感じでした。
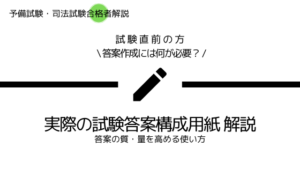
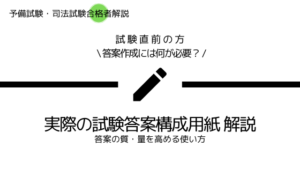
⑤蛍光ペン5色
蛍光ペンを使うなら、ノック式がオススメです。
私は、これを利用していました。
蛍光ペンを使わない派は不要です。
普段の勉強では蛍光ペンはあまり使わなかったですが、答案構成を効率よくするために蛍光ペンを利用していました!
⑥ハンカチタオル
これは男性諸君は、特におすすめです!
手汗を拭くため、また、机の振動で、ペン類がカタカタなるのを防ぐために使っていました。
机は、試験会場によるかもしれませんが、結構カタカタしていました。
常日頃からハンカチを持っている人は良いですが、ない人は持参すると良いでしょう!
一応、机上に置いてよいかは要確認してください!
私が受験した際は、試験前にハンカチを開いて中に何もないことを示す必要はありましたが、利用はOKでした。
⑦受験票
これはマストですね。
以上が、令和元年司法試験に私が、「机上に置いた物」でした。
ちょっと物が多すぎますかね。人によっては、蛍光ペンは不要でしょうし、起案用のペンは4本もいらないでしょう!
少しでも参考にしていただければ幸いです。
最後に
私は、かなり心配性でしたので、試験前に持参する物であったり、机上に置くものを検討していました。
勉強の休みにもでも、何を持っていくのか、起案用のペンはどれにするか、ペンは足りているのか等を検討してみるとよいでしょう!










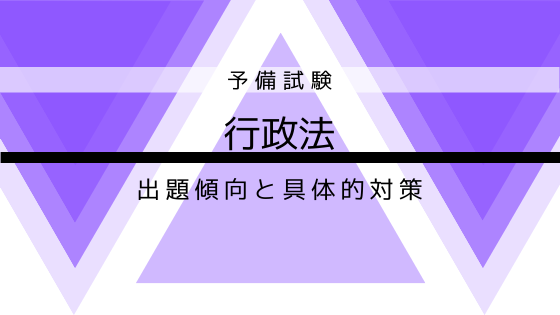
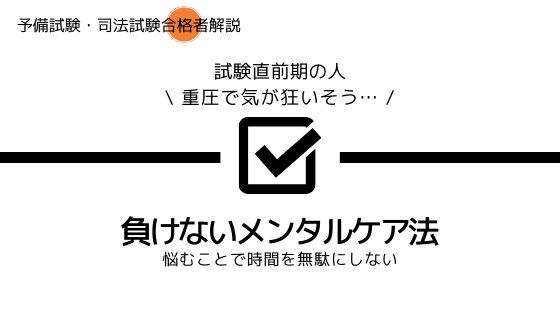
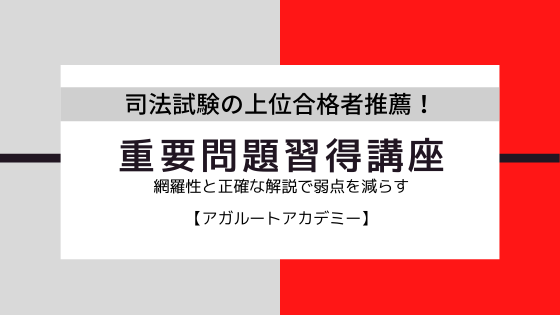
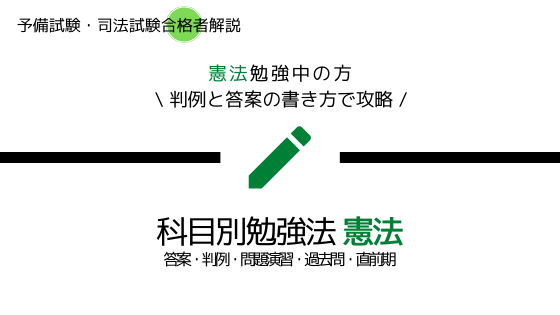
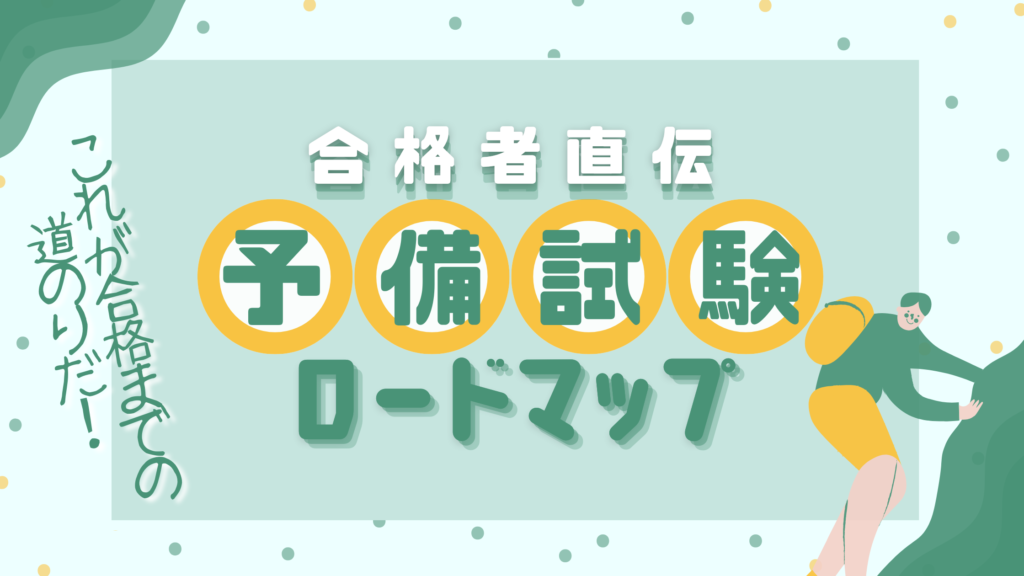
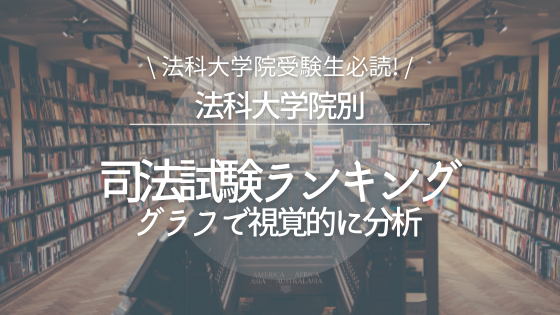








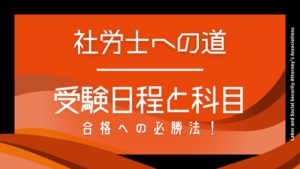

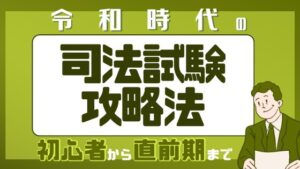


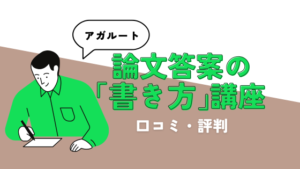



コメント