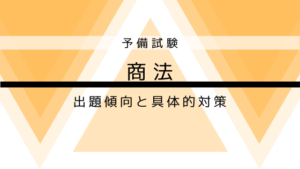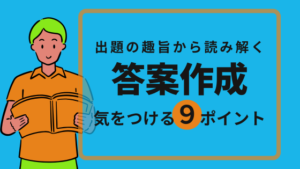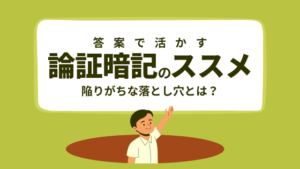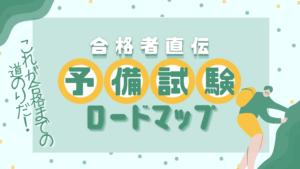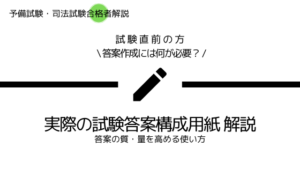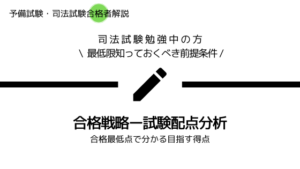予備試験の民事訴訟法の出題傾向と具体的対策【図表あり】
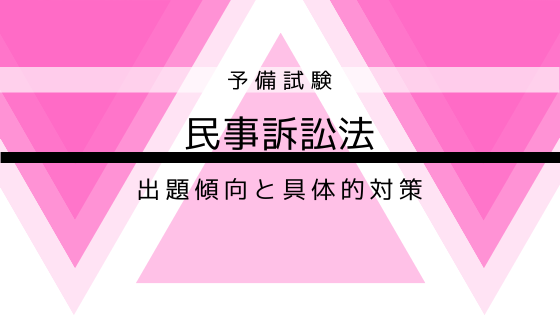
今回は、司法試験予備試験の民事訴訟法の論文対策について解説したいと思います。
民事訴訟法の出題傾向
予備試験民事訴訟法の出題事項
| H30 | H29 | H28 |
| 原告が両負けを避けるための措置
単純併合 同時審判申出共同訴訟 主観的予備的併合 |
将来給付の訴えの利益
相殺における既判力の生じる範囲 |
弁論主義の適用範囲や事実の分類
釈明義務ないし法的観点指摘義務 口頭弁論終結後の承継人に対する既判力の拡張 |
| H27 | H26 | H25 |
| 訴訟物の特定基準
一部請求に関する判例等の基本的理解 |
訴訟係属後に、第三者を訴訟手続に参加させる方法
承継の前後における陳述の効果 |
債権者代位訴訟の基本的理解
訴訟参加の基本的理解 |
| H24 | H23 | |
| 明示的一部請求
既判力が生じる範囲 相殺抗弁の特殊性 |
当事者死亡の場合における訴訟手続
第一審判決で表示された当事者と異なる者が控訴した場合の取扱 |
司法試験予備試験民事訴訟法は、司法試験と同様の出題傾向があります。弁護士と修習生の会話録による誘導がある問題も出題されていますし、出題の中では、未知の論点が問われることが多いです。
民事訴訟法上の基本原則の理解が問われる傾向が顕著です。弁論主義や処分権主義といった民事訴訟法上の基本的な原理・原則を正しく理解し、基礎的な知識を習得しているかが問われていると言えます。
また、これらの基本的な原理原則を具体的な事案に適切に適用することができるかが問われています。
民事訴訟法の具体的対策
以下では、予備試験民事訴訟法の具体的な対策を見ていきましょう。
事例演習
上記のとおり、民事訴訟法上の基本的な原理・原則を正しく理解しているのかを判断するために、具体的な事例における、その原理原則の適用が問われることが多いです。
司法試験平成28年採点実感においても「民事訴訟法の基本的な原理・原則や概念を正しく理解し、基礎的な知識を習得しているか」を評価していることを明らかにしています。
具体的な事例を使った演習を行い、原理原則の適用の練習を積むべきです。
定義・趣旨
民事訴訟法上の基本的な原理・原則を具体的な事例に適用するためには、その前提として、その基本的な原理・原則の定義や趣旨などを明示しておくと論述がしやすいです。
定義があやふやだと、論証も曖昧なものになってしまいます。民事訴訟法上の原理、原則や概念については、暗記事項として、正確に吐き出せるように準備しておきましょう。
例えば、「附帯控訴とは?」と聞かれた場合に、その定義と趣旨を説明することができるように準備しておかなければなりません。
ちなみに私は、附帯控訴の定義は、「被控訴人が、控訴審の口頭弁論終結に到るまですることができる、原判決に対する特殊な不服申立て」と覚え、その趣旨は、「当事者間の公平」と「訴訟経済」と暗記していました。
手続の流れを理解する
訴訟法である以上、手続の流れを理解しておく必要があります。民事訴訟法上の原理・原則・概念について、手続上のどの段階で問題になるかを意識しながら勉強するといいでしょう。どの手続で、どの原理が問題になるかを理解していると、事例の設定に応じた適切な分析をすることができるようになります。
民事訴訟法の判例の習得
判例の習得は、どの科目においても重要なことですが、民訴では特に重要です。
司法試験の民事訴訟法では、従来、判例の射程を問う問題が出題されていました。判例を理解していなければ、理解できないような出題もありました。
予備試験でもこの傾向が見られます。
少なくとも百選掲載判例の「事案」と「判旨」は押さえておきたいところです。余裕がある人は、批判の強い判例については、その批判についても理解しておくべきでしょう。