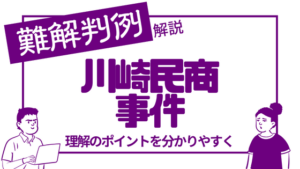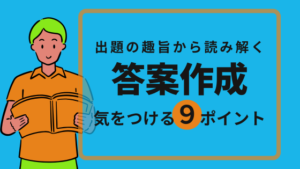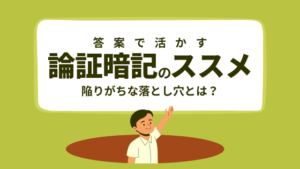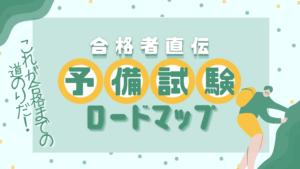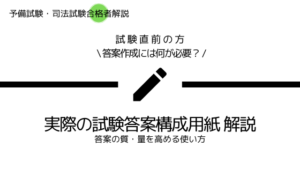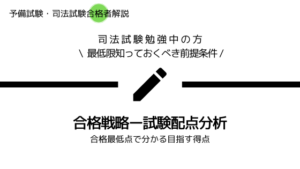司法試験予備試験の刑事実務の論文対策【図表あり】
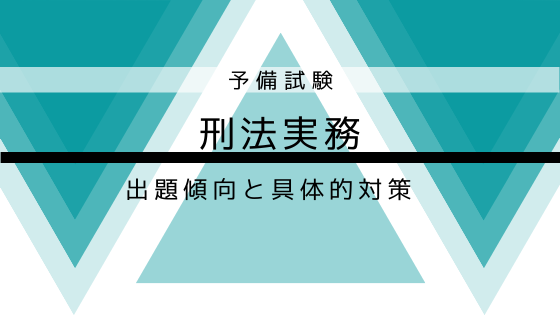

今回は、司法試験予備試験の刑事実務の出題傾向と具体的対策について解説したいと思います。
例によって過去の出題事項を確認しましょう。今回は、直近の4年間をまとめています。
刑事実務の出題傾向
<平成29年度出題事項>
|
<平成28年度出題事項>
|
<平成27年度出題事項>
|
刑事実務基礎では、刑事弁護人の各場面において取るべき措置や、主張が問われています。また、弁護士倫理が問われることもあり、範囲は膨大であります。対策のしにくい科目であると思います。
「犯人性の認定」や「殺意の認定」など事実認定が求められることもあります。証拠から事実を認定できなければなりません。
「保釈請求における罪証隠滅のおそれ」など各種制度における主張が問われることもあります。
また、「証人尋問における被害再現写真の利用」など公判分野における判例知識が問われることもあります。
刑事実務の具体的対策
以下では、司法試験予備試験刑事実務の具体的対策について解説していきます。
刑事弁護人の活動を時系列に沿って整理しとこう
刑事実務では、各場面で刑事弁護人がどのような措置を取りうるかが問われます。
依頼者が勾留されている場合、起訴された場合、公判、など各場面で弁護人がどのような法的措置や異議を述べることができるのか整理しておくべきです。
時系列に沿って各活動を復習してみてください。
公判分野の判例知識の習得
公判分野の判例は、刑事訴訟法でも問われる可能性もあり、刑事実務でも問われる可能性があります。必ず勉強しておくべきです。
以下、公判分野で最低限学習しておくべき判例を列挙します。
押さえておくべき百選の事件
| 1. 百選40事件(起訴状における余事記載)
2. 百選52事件(必要的弁護) 3. 百選54事件(公判前整理手続における証拠開示) 4. 百選55事件(刑訴法316条の17と自己に不利益な供述の強要) 5. 百選56事件(公判前整理手続後の訴因変更) 6. 百選57事件(公判前整理手続における主張明示と被告人質問)cf新司過去問 7. 百選58事件(公判前整理手続後の証拠調べ請求) 8. 百選68事件(証人尋問における被害再現写真等の利用) 9. 百選95事件(量刑と余罪) 10. 百選96事件(無罪判決後の勾留) |
また、以下のように余裕があれば論証を用意しておきましょう。
百選58事件論証
| 1. 公判前整理手続後に弾劾証拠請求をすることは許されるか
刑訴法316条の32第一項は、「止むを得ない場合に」限り、新たな証拠調べ請求を認めている。このような制限を設けないと、新たな証拠を出発点に当事者間で新たな主張、証拠調べ請求のやりとりが行われ、公判前整理手続等における争点及び証拠の整理の実効性が損なわれるからである。 「やむを得ないばあい」の該当性判断に当たっては、同手続きの趣旨を没却することにならないかを考慮して判断するべきである |
| 2. 百選58事件の当てはめ
刑訴法328条による弾劾証拠は、条文上「公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うため」のものとされているから、証人尋問が終了しておらず、弾劾の対象となる公判供述が存在しない段階においては、同条の要件該当性を判断することはできないのであって、証人尋問終了前に当事者に取調べ請求を要求することは相当でない。 そうすると、同条における弾劾証拠にける取調べ請求については、同条316の32第一項の「やむを得ない事由」があるものと解すべきである。 |
| 3. もっとも、公判前整理手続を実施した事件における弾劾証拠の採否に当たっては、同法316の2に規定する「充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行う」ことの要請から、証拠としての「必要性」についても厳格な吟味を要するというべきである。 |
各種請求の要件の確認
保釈請求や類型証拠開示請求の要件該当性は頻繁に問われています。条文を確認した上で当該要件との関係で具体的にどのような事実を主張すべきなのか考えおきましょう。
公判前整理手続の理解はマスト
刑事実務では、毎年のように公判前整理手続が問われます。公判前整理手続では、何ができて何ができないのか、制度趣旨はなんなのか、公判前整理手続が必要となるのはどういう場合かなど整理しましょう。
弁護士倫理は余裕があれば
実務基礎の問題では、弁護士倫理も問われます。がっつり勉強する必要はありませんが、弁護士職務倫理規定の条文くらいは読んでおきましょう。条文のあたりをつけられれば、試験現場でそれっぽい論証ができます。弁護士倫理の勉強は、そのくらいで十分だと思います。