司法試験の勉強の順番は?どの科目から勉強をするべきか。
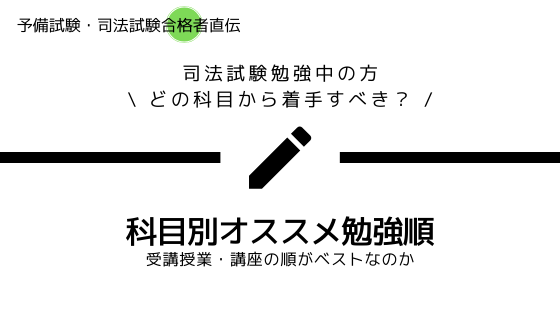
今回は、司法試験の勉強の順番について解説したいと思います。どの科目から着手したらいいのか結構悩みますよね。その点について今回は、解説させて頂きます。
一般的な学習順序
一般的な学生は、憲法→民法→刑法の順序で勉強しているのではないでしょうか。
私も、大学の授業が概ねこの順序で開講されていたので、上記の順序で勉強していました。
まずは、法律の上位規範である憲法を学び、民事法の一般法である民法、刑事法の一般法である刑法を勉強する。法律の体系的理解を促す理想的な順序と言えるでしょう。
しかし、試験対策的には、疑義があります。
憲法を最初に勉強するべきではない?
まず、憲法は特殊な科目です。論文の答案は、基本的に、問題所在の適時(条文の摘示)→要件の提示→要件の解釈→事実への適用→結論という過程を経ます。しかし、憲法の答案は、このような過程を経ません。
憲法の答案は、特殊です。この特殊な科目を初めに勉強するべきなのか。疑問があるところです。
さらに、憲法は、試験対策の効果が薄い科目であると私は考えています。時事問題が出題されることの多い憲法の論文式試験。そこでは、法律論の立論の上手さというより、想像力や社会問題への関心の程度など、法的素養とは異なる能力が試されているように思います。
最初に勉強すべきは刑法
個人的に最初に勉強すべきは、刑法です。その中でも刑法各論がおすすめです。
刑法の答案は、典型的な、問題所在の適時(条文の摘示)→要件の提示→要件の解釈→事実への適用→結論型の答案です。
また、刑法総論と異なり刑法各論は、理論面は相対的に強くなく、判例の規範が重要となってきます。
まずは、刑法各論の勉強して、法的思考方法を習得することが良いか思います。
刑法の次は、民法
刑法の次に勉強する科目は、民法がいいでしょう。民法は、範囲が広い上で、商法や民事訴訟法の理解の前提となる科目です。そのため、出来るだけ早めに着手すると良いと思います。
また、必ずしも民法総則から勉強する必要はないと思います。民法総総則は、一般的包括的な規制が多く、問題となる事案を想像しにくいです。まずは、売買契約や賃貸借契約など、身近な契約類型を勉強すると良いのではないでしょうか。
民法・刑法の次は、基本的に何でもいい
民法と刑法の次は何でもいいと思います。
しかし、受験戦略的には、出題の幅が広く勉強量が相対的に多いものから着手するべきでしょう。そうなると、出題法律の方法が限定的で勉強量が相対的に少ない、行政法は、慌てて勉強する必要はないかと思います。
また、上述したように憲法も後回しでいいと思います。したがって、公法系2科目は、最後に回していいと思います。憲法と行政法は、一部出題が被る(例えば、損失補償、委任命令など)ので、最後にまとめて一気に勉強すれば良いと思います。
ただ、刑法→民法の次はそこまでこだわらなくて良いと思います。各人の興味関心に従い勉強すれば良いと思います。
個人的に考えるベストの順序
とはいえ、個人的にベストな順番があります。
最後に、個人的に考えるベストの勉強の順序をご紹介したいと思います。
1 刑法
まずは、刑法です。理由は、前述した通りです。
2 民法
2番目は、民法。刑法→民法の順序は、多くの受験生に支持されるのではないかと思います。
3 商法
3番目は、会社法が良いと思います。株主総会や取締役、株式など比較的馴染みやすい科目であることに加えて、会社法の条文数に早めに慣れておくことが良いと思うからです。
さらに、会社法の論点では、民法の理解が前提となるものが多いので、民法→商法の順序で良いかと思います。
商法と表記していますが、会社法をやれば良いと思います。商法と手形小切手法は、他の科目の勉強が終えてから、余裕があればやればいいでしょう。1週目からやる必要はありません。
4 刑事訴訟法
4番目に刑事訴訟法です。こちらも想像しやすい事案が多いですし、捜査法に関しては、刑法と同様に、要件提示→解釈→当てはめという流れになるので、答案も書きやすいです。
また、個人的にはそこまで暗記すべき事項も少ないと思いますし、出題の範囲も限定的だと考えているので、4番目に位置付けています。
伝聞証拠は、試験でも頻繁に出題される超重要テーマですが、1週目のうちは、その趣旨を理解するにとどめて、実質的な検討は、2週目に回しても良いと思います。一回で理解するのは難しいと思うからです。
5 民事訴訟法
5番目に民事訴訟法です。民事訴訟法法は範囲が広く、司法試験の問題も難しいです。民法の次に難しい出題がされていると思います。そのため、出来るだけ早く勉強に着手するべきかと思われます。しかし、学説は多岐にわたり理論的理解が不可欠であり、高い法的考察力が求められます。
したがって、個人的にはある程度、法律の勉強が進み、法的思考力が備わってきてから勉強に着手すると良いかと思います。
6 憲法
公法系を後回しにする理由は、前述した通りです。行政法より先に憲法勉強すべき理由は、勉強すべき量が多いからです。憲法には、人権分野と統治分野があります。両分野ともに、かなりの量があります。
そのため、勉強量の少ない行政法より、先に着手するべきです。
7 行政法
最後に行政法です。その理由は、前述の通りです。
最後に
以上より、
刑法→民法→商法→刑事訴訟法→民事訴訟法→憲法→行政法
これが、勉強の効率性という観点から、ベストの勉強の順番であると思います。
効率的な勉強法を知りたい方は、勉強法に関する本おすすめ10選をご覧ください。
この記事をご覧の方におススメの記事はこちら
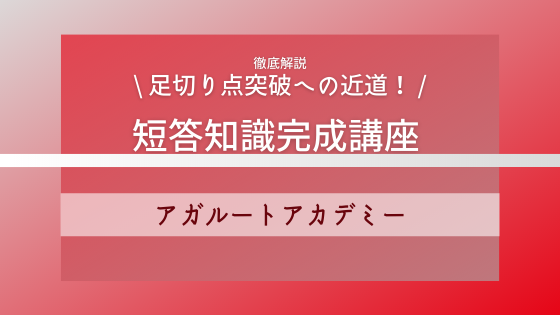
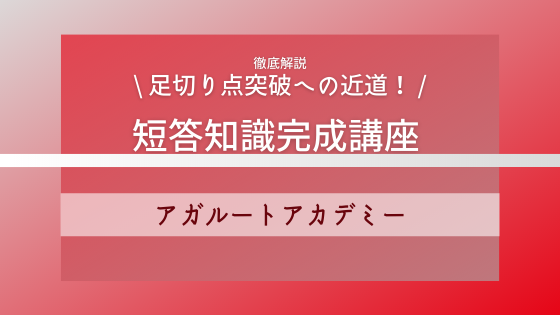
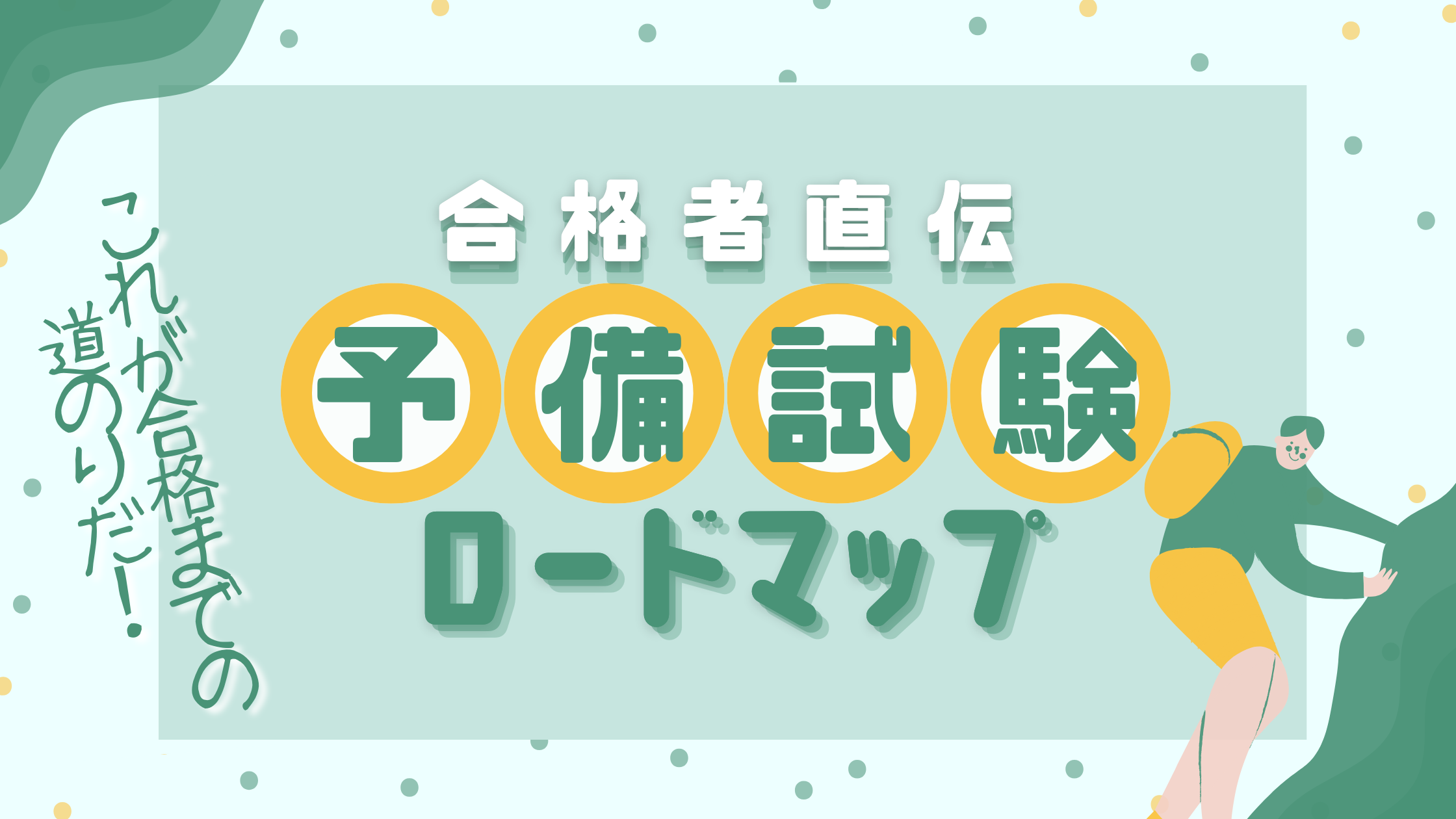
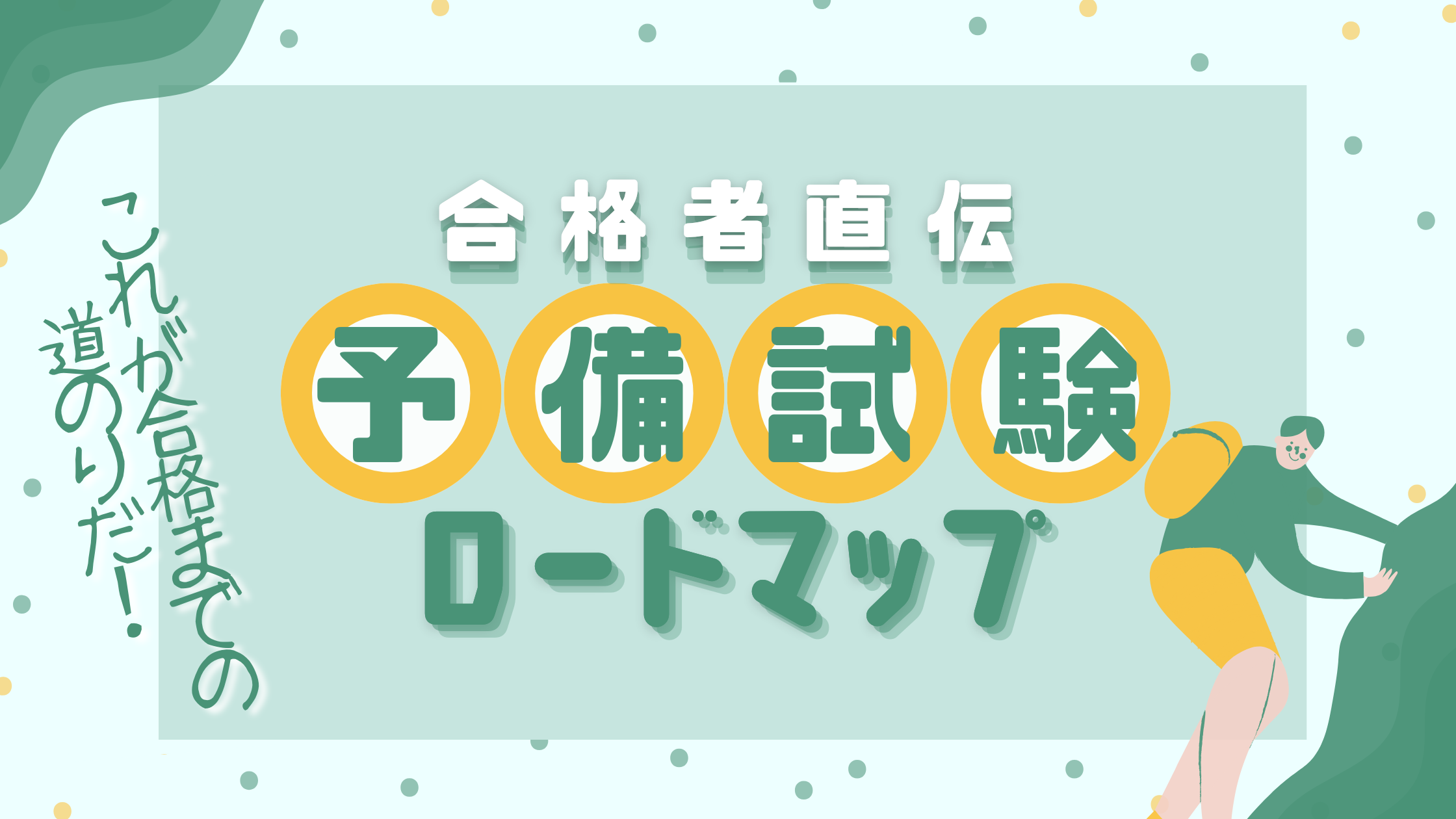










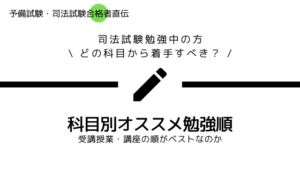
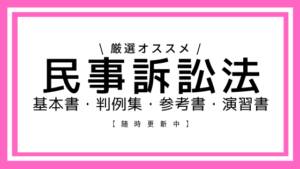
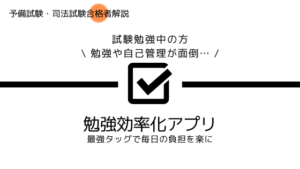
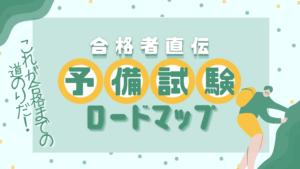

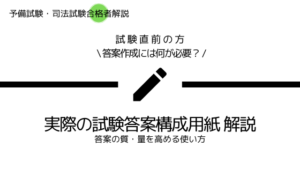

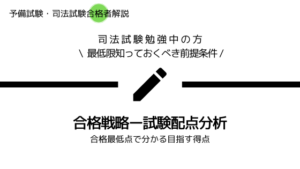
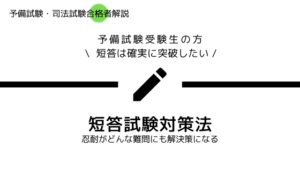
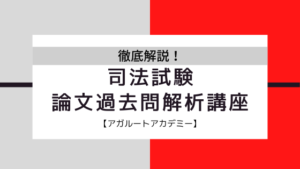
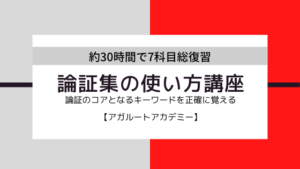

コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 司法試験の勉強の順番は?どの科目から勉強をするべきか。 […]
[…] 司法試験の勉強の順番は?どの科目から勉強をするべきか。 […]