【令和7年最新】予備試験の刑法の出題傾向と具体的対策【図表あり】

『予備試験刑法の出題傾向が知りたい。』
『予備試験刑法の出題傾向を踏まえた対策を行いたい』
本記事を読まれている方は予備試験に挑戦されている方かと思います。
その中でも刑法の出題傾向や対策について知りたい方かと思いますが、本記事では、令和4年から平成23年度までの出題事項を紹介し、実際に出題されている範囲を基に、予備試験の刑法の出題傾向と具体的な対策方法について解説をさせて頂いております。
当サイトでは、刑法のみならず、他の科目についても、予備試験の出題傾向と具体的な対策方法について解説をさせて頂いておりますので、もしよろしければ、合わせて参考にして頂ければ幸いです。
それでは、予備試験の刑法の出題傾向と出題傾向を踏まえた具体的な対策方法について解説したいと思います。
予備試験刑法の出題範囲、出題傾向
予備試験刑法の令和4年度から平成23年度までの過去の出題事項をまとめました。
予備試験刑法の出題事項、論点
| 令和6年度 | 暴行罪の成否に関する判断 傷害罪の成否に関する判断(暴行と傷害の結果の因果関係) 共謀共同正犯の成否に関する判断 承継的共同正犯 同時傷害の特例(刑法207条) |
| 令和5年度 | 正当防衛の成否及び過剰防衛の成否の判断基準 |
| 令和4年度 | 刑事未成年者を利用した間接正犯 実行の着手の有無 事後強盗罪の未遂、既遂の区別 窃盗の機会 |
| 令和3年度 | 自己所有物の窃取 放火罪における「公共の危険」及びその認識 不作為犯 |
| 令和2年度 | 有印私文書偽造罪・同行使罪の成否 欺罔行為該当性 護送防衛又は護送過剰防衛 |
| 令和元年度 | 有印私文書偽造罪・ 同行使罪の成否 横領罪と背任罪の関係 遅すぎた構成要件の実現 |
| 平成30年度 | 横領罪 強盗罪共同者が過剰行為をした場合の共同正犯の成否 |
| 平成29年度 | 離隔犯における実行着手 未遂犯と不能犯との区別 間接正犯の成否因果関係 |
| 平成28年度 | 放火 抽象的事実の錯誤 中止犯の成否共犯者への影響 |
| 平成27年度 | 共同正犯 共犯と身分 贈収賄罪 業務上横領 |
| 平成26年度 | 詐欺 強盗殺人未遂 正当防衛 盗品等保管罪 横領罪 |
| 平成25年度 | 詐欺罪の客体 実行行為 既遂時期 共謀共同正犯 |
| 平成24年度 | 被害者の承諾 方法の錯誤 共謀の意義 共犯関係からの離脱 傷害罪 |
| 平成23年度 | 因果関係 事実の錯誤 証拠隠滅罪 |
この一覧は、各年の出題趣旨から主要な論点を抽出したものであり、事例によってはさらに細かな論点が含まれている可能性があります。ご了承ください。
予備試験刑法の出題傾向
具体的な事実に基づいた事例問題
予備試験の刑法問題は、抽象的な法理論を問うのではなく、具体的な出来事を描写した詳細な事例問題が中心です。これらの事例は、登場人物の関係性、時間経過、行為の内容、結果など、多岐にわたる事実を含んでいることが特徴です。
受験生は、まずこれらの事実を正確に読み解き、時系列に整理し、登場人物の行動や心理状態を把握することが求められます。事例の中には、犯罪の成否を左右する重要な事実と、そうでない事実が混在しているため、事実の法的関連性を見抜く能力が不可欠です。
例えば、暴行事件では、被害者と加害者の出会いの状況、暴行に至る経緯、具体的な暴行態様、被害者の傷害などが詳細に記述されており、これらの事実を基に暴行罪や傷害罪の成否を検討する必要があります。
また、窃盗事件では、キャリーバッグが置かれていた状況、甲と乙のやり取り、甲の弁解など、窃盗罪の故意や不法領得の意思を判断する上で重要な事実が細かく描写されています。
特定の犯罪類型の理解と適用
これまでの予備試験の出題では、窃盗罪、詐欺罪 、暴行罪・傷害罪 、殺人罪 、放火罪など、特定の犯罪類型に関する理解と、具体的な事実への適用能力が繰り返し問われています。
これらの犯罪の成否を判断するためには、各犯罪の構成要件(客観的構成要件と主観的構成要件)、違法性阻却事由、責任阻却事由といった要素について、条文と判例に基づいて正確に理解することが必要です。
例えば、窃盗罪であれば、「他人の財物」を「窃取」する行為と、その故意(不法領得の意思を含む)が構成要件となります 。ある事例では、甲がキャリーバッグを持ち去った行為が「窃取」に当たるか、また甲に「不法領得の意思」があったかが争点となり得ます。
判例の知識の重要性
予備試験の刑法においては、判例の知識が非常に重要です。窃盗罪の成否に関する設問では、「判例の立場に立って」事実を摘示して説明することが明確に求められています。
これは、単に刑法の条文を暗記するだけでなく、判例が条文をどのように解釈し、具体的な事案に適用してきたのかを理解することが不可欠であることを示しています。
判例は、構成要件の解釈、違法性阻却事由や責任阻却事由の適用範囲など、刑法上の重要な判断基準を示しているため、判例の理解なしに適切な法的構成を行うことは困難です。
予備試験刑法の具体的対策
以下では、予備試験刑法の具体的対策について説明したいと思います。
刑法の論点の網羅
まず、多論点型の出題の対策として、論点を網羅的に学習する必要があります。刑法では、判例学習よりも論点学習の方が大切だと思います。論証集に掲載されている論点については、全て理解し論証できるように準備するべきです。
出題に応じて、論証の長短を調節できるように、長めの論証と短めの論証のいずれも論証できるように準備しておくべきです。
論点の網羅的学習が終わったら、判例学習に移行してください。特に、重要論点の判例は押さえるようにしておきましょう。
刑法の学説の理解
平成30年度以降、司法試験では、学説の理解が問われるようになっています。予備試験でも同様の出題が想定されるので、学説の学習もしておきましょう。
特に、重要論点で判例と学説との間に対立があるものを重点的に学習しましょう。
また、判例の見解からはどのような結論になるのか、学説の見解を採用するとどのような結論になるのかを、普段から意識しながら学習しましょう。
平成31年度の司法試験では、事後強盗に関する判例・学説の立場から、どのような結論になるのかを検討する必要がある出題がされました。
網羅的な検討
多論点型の出題であろうと、小問型の出題であろうと、結局のところ、罪責の有無が問われているので、犯罪の成立に必要な全ての事項を網羅的に検討する必要があります。
事案分析の段階から、「実行行為」「結果」「因果関係」「故意」「客体」「主体」が、何なのか特定しましょう。このような分析をすることで、論点の抽出を正確に行うことができます。特に、財産犯においては、客体の特定が、成立する犯罪の種類に影響を与えますので、正確にする必要があります。
最後に
いかがでしたでしょうか。
今回は、予備試験刑法の出題傾向と具体的な対策方法をご紹介させて頂きました。
予備試験の対策をする上、情報収集は非常に大切です。しっかり情報収集をし、勉強法、対策法を確定してからガーっと勉強するのが効率的かと思います。
当サイトでは、おすすめの予備校アガルートの講座を使った効率の良い勉強法を解説をしておりますので、予備校を使って効率よく勉強がしたい方は参考にしてみてください。


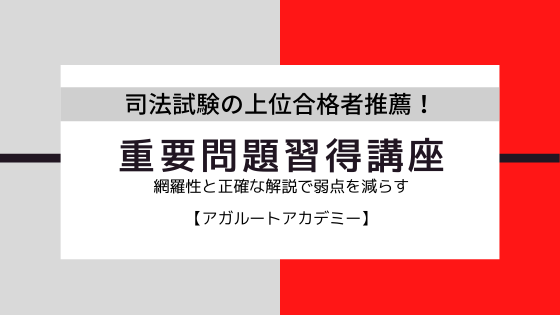
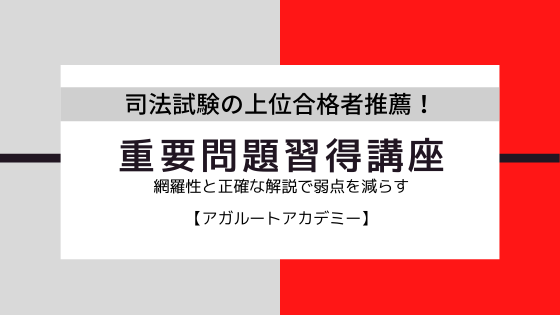
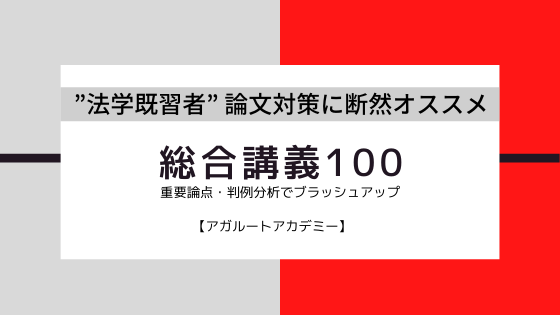
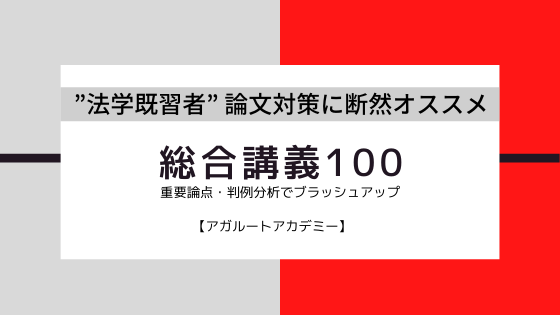












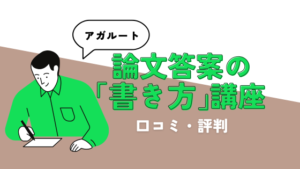

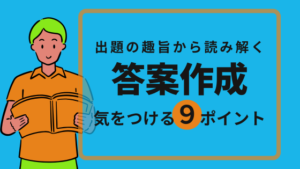
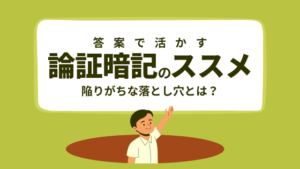
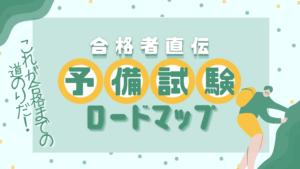
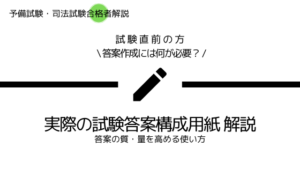

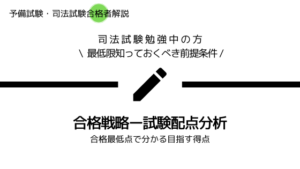
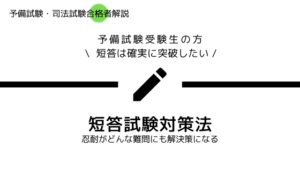

コメント
コメント一覧 (2件)
[…] あわせて読みたい 予備試験の刑法の出題傾向と具体的対策【図表あり】 […]
[…] >刑法の出題傾向 >予備試験ロードマップ おすすめ司法試験予備校 […]