【2023年】司法試験予備試験のメリット5選とデメリット4選
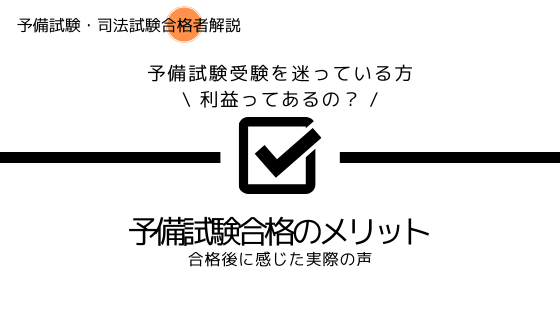
「予備試験に合格すると、どのようなメリットがあるのか」
「なぜ、莫大なコストをかけてまで予備試験合格を目指すのか」
「法科大学院に進学して司法試験を受けるべきなのか、それとも予備試験を選ぶべきなのか。予備ルートのデメリットが知りたい」
この記事を読まれている方はきっと予備試験に挑戦することを決心した人、予備試験に挑戦することを検討している方だと思います。
予備試験は、人生を賭ける挑戦です。挑戦する前に予備試験に合格するとどうようなメリットがあるのか理解をしておいがほうがよいでしょう。
今回は、予備試験合格のメリットと予備試験を目指すことのデメリットについて解説をさせていただきたいと思います。
この辺りのことを解説したいと思います。
「予備試験の概要」と「予備試験の難易度」についてはこちらの記事で解説をしています。
予備試験のメリット5選
短期で司法試験受験のチャンスがある
最大のメリットは、司法試験の受験資格を取得することができる点です。
現行の司法試験制度は、受験資格を制限しており、受験できるのは、①法科大学院を卒業した者、または②予備試験に合格した者のみです。
大半の方は、①ルートにより受験資格の取得を目指します。
ただし、法科大学院の卒業には、少なくとも2年かかりますし、法科大学院を受験するためには、大学卒業が、通常求められます。
なお、2023年(令和5年度)司法試験よりロースクールの在学中受験がスタートしたため、時間短縮のメリットは小さくなったとも言えます。
このように、①ルートでは、時間がかかるというデメリットがあります。そのため、②ルートより、受験資格の取得を目指す人も多くなっています。
予備試験に合格すれば、大学生でも、司法試験を受験することができます。司法試験受験までの時間を短縮することができることが、最大のメリットといえるでしょう。
時間短縮以外にも、予備試験合格のメリットがあります。
他方で、ご存知のとおり予備試験合格は非常に難易度が高いです。したがって、複数回受験をしても予備試験に合格できずに司法試験に挑戦することができないという方もいます。
時間やお金に余裕があるという方は法科大学院経由で司法試験を目指すのも一つです。
就職活動で有利になる
一般的に予備試験は、合格率も低く合格者数が少ないので、合格組は優秀と考えられることが多いです。
そのため、就職活動でこの点が有利に働くことがあります。中規模以上の法律事務所の就職活動では、「書面審査→面接→サマクラ→面接→採用」の流れで行われます。
予備試験に合格していれば書面審査で落とされることは稀だと思います。もっとも、4大法律事務所であれば、予備試験に合格しているだけでは、落とされることもあるかもしれません。
予備試験合格は、その人の優秀さを示す一つの事情に過ぎないのは事実ですが、事実上かなり有利であることは間違いないと思います。
予備試験合格というステータスは就職活動で非常に有利になります。
予備組の司法試験合格率は驚異の数字
さらに、予備試験合格者の司法試験合格率はだいたい60%程度です。
また、20代に限定すると、90%程度の合格率となります。
このように、予備試験に合格すれば「司法試験に合格できる実力にかなり近い」ことが分かります。そのため、予備試験に合格された方は自信をもって司法試験の受験に挑むことができます。
予備試験に合格すると3つのメリットがある。
1. 予備試験に合格すると、司法試験を受験する資格を得流ことが出来る
2. 予備試験に合格していると、就職活動で有利になる
3. 予備組合格者は、司法試験の合格にかなり近い存在と分かる
→様々なカタチで時間を有意義に過ごすことができる。
誰でも受験ができる
予備試験は受験資格がありません。誰でも受験することができます。高校生でも社会人でも非法学部でも受験生の属性を選びません。
したがって、法科大学院を修了することが経済的に時間的に厳しい方にはおすすめのルートになります。
司法試験と科目が共通する
また、予備試験を目指すメリットとしては、上述の通り予備試験合格者の司法試験合格者の合格率が高いことからもわかるように、予備試験試験合格≒司法試験ん合格です。
なぜなら、予備試験で出題される法律科目と司法試験で出題される法律科目は共通しているからです。したがって、予備試験のために勉強をした方はそのまま司法試験の勉強に繋がっています。よって、予備試験に挑戦することは司法試験合格との関係で全く無駄になりません。
以上が、司法試験予備試験合格のメリットでした。
予備試験のデメリット4選
続いて予備試験のデメリットを紹介させていただきます。
予備試験合格の難易度は高い
予備試験の合格難易度は非常に高いです。日本で最も難しい試験と言っても過言ではないかと思います。
その合格率は5パーセント以下です。したがって、何回も挑戦をしてもなかなか合格に辿り着けない可能性があります。
しかし、予備試験も資格試験の一つです。攻略方法は確かにあります。そして、この攻略方法に精通しているのは司法試験予備校です。
しかし、当サイトが推奨している予備校「アガルートアカデミー」は高い合格実績を有しています。
したがって、予備試験に挑戦することは予備校とタッグを組めば無謀なことではありません。
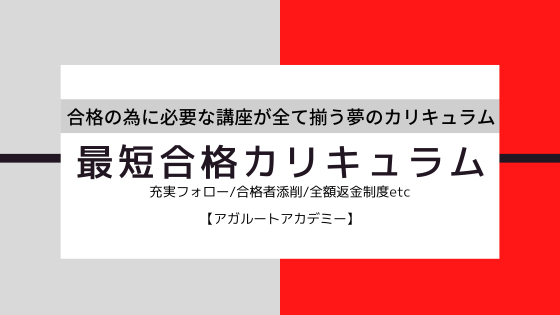
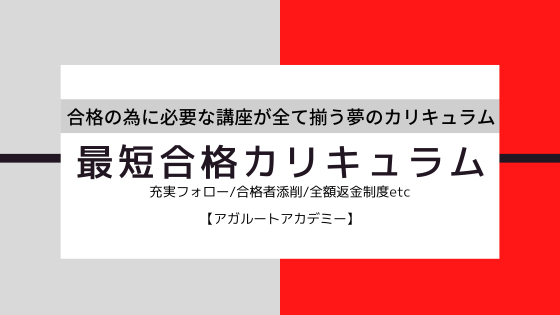
高い自己学習能力が必要
予備試験に合格するためには高い自己学習能力が求められます。
法科大学院経由で司法試験を目指す場合に法科大学院側が練りに練った合格カリキュラムを用意しています。法科大学院は法曹実務家養成期間のため、司法試験合格のためだけの教育機関ではありませんが、メインは司法試験対策と言っても語弊はないと思います。
上位のロースクールでは確かに、司法試験の枠から飛び出した非常にレベルの高い実務家より講義なども行われています。
しかし、基本的には法科大学院の教授質が司法試験の合格率が高くなるように授業の構成を考えて、カリキュラムを策定しています。
したがって、法科大学院経由の場合、自己学習能力が高くない人でもあっても、カリキュラムの授業を受講し、期末試験対策をしているうちに司法試験対策を行うことができます。
他方で、予備試験のルールはそのようなカリキュラムはありません。当然、自らでどのように勉強するのか、どの本で勉強するのか、どの予備校を使うのは、使わないのかを考える必要があります。
したがって、自身で学習計画を立て、その実行を管理する自己管理能力も必要です。
予備ルートは孤独な学習環境
予備試験ルートでは基本的に一人で学習を進めることになります。
学習の途中で疑問点が出たときに質問できる相手がいない、学習に対するモチベーションを保つのが難しい、等の問題があります。
法科大学院ルートの場合、法科大学院の教授、事務局、同期などがいるため悩みがあれば相談ができますし、わからないことがあれば教授に聞くこともできます。
他方で、予備ルートの場合は、基本的に全て1人で勉強することになります。したがって、孤独な環境の中で勉強を続ける必要があります。
しかし、新司法試験制度になり法科大学院が新設されるまでの間は、受験生は皆孤独に勉強をしていました。そのことから考えるとそこまで過酷なことではありません。
今では、優れた司法試験予備校が登場していますから、予備校をうまく活用すれば孤独感を感じることなく、予備試験合格まで狙えるかと思います。
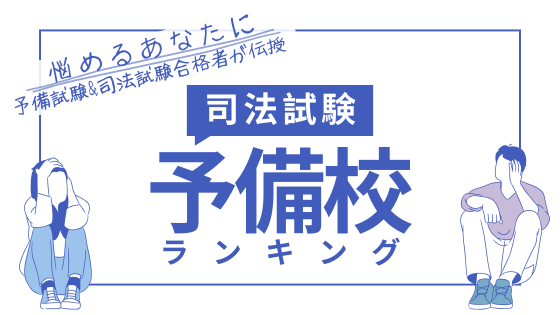
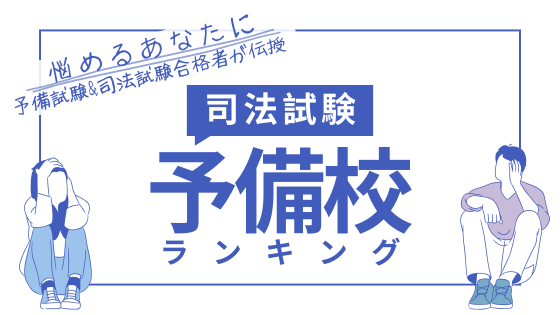
相当の覚悟が必要
予備試験の合格難易度は非常に高い上に、孤独な環境で勉強する必要があり、さらに、勉強プランは自ら考えて実行する必要がございます。
当サイトでは、予備試験合格のためのノウハウを発信していますから、是非、参考にしてみてください。
また、予備試験合格を目指すなら、予備校の利用は必須と考えてください。他方で、予備校を利用するだけで予備試験のデメリットはほぼほぼ解消されます。
最後に
いかがでしたでしょうか。
今回は、予備試験のメリット5選とデメリット4選をご紹介させていただきました。
この記事を読まれている方は真剣に予備試験に挑戦をしようと考えている方だと思います。
予備試験に論文300番代で合格し、司法試験に100番代で合格した筆者としてお伝えできることは、今の時代、予備校を使わないのは勿体無いということです。
現在のオンラインメインの予備校が登場するまでの間は、予備校の代金は非常に高かったです。それこそ法科大学院の2年分の受講料に近い金額がかかってしまうことがありました。
しかし、現在のオンライン予備校は、価格が低価格です。通学講義の場合は、講師の人件費が非常に高くつきますが、動画の講義の場合は一度に収録して、多数の受講生に届けることができるため、受講生1人あたりの受講料を安く抑えることができます。
また、オンライン講義の場合は、倍速再生や巻き戻して再生をしたりできるなどメリットが非常に大きいです。
そして、予備試験に合格すれば、司法試験合格はほぼ間違いなく、さらに、就職では非常に有利になります。あなたの人生を大きく変える魔法のチケットです。挑戦する価値は大いにあります。
しかし、司法試験の勉強は非常に大変です。合格までの道のりは相当厳しいです。
いろんな予備校を使ってきた筆者としては、当サイトで推奨しているアガルートアカデミーの講座をぜひ、ご利用いただきたいと思っています。最も効率よく、孤独感を感じることなく、司法試験対策を楽しみながら進めることができるはずです。
少しでもアガルートの講座が気になった人は以下の記事を参考にしてみてください。
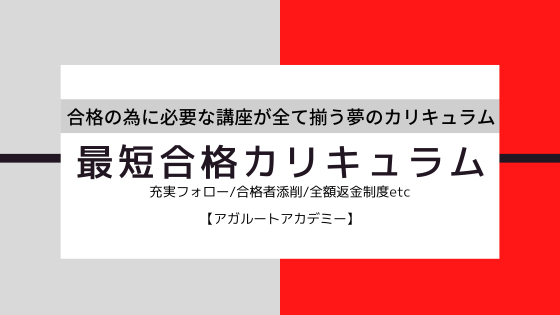
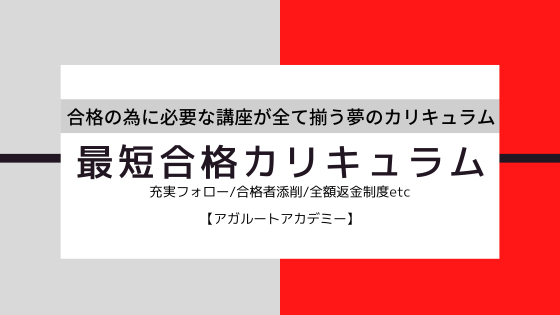
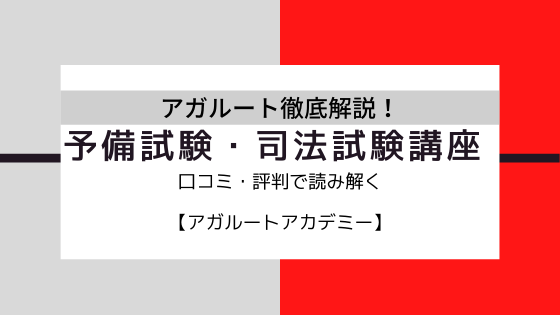
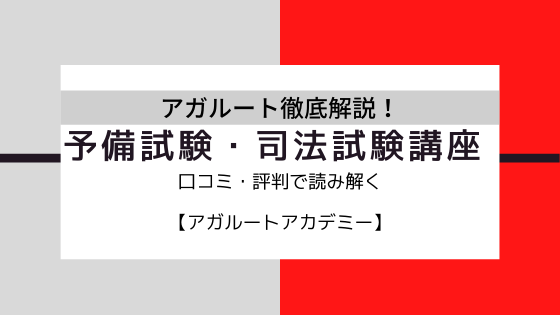
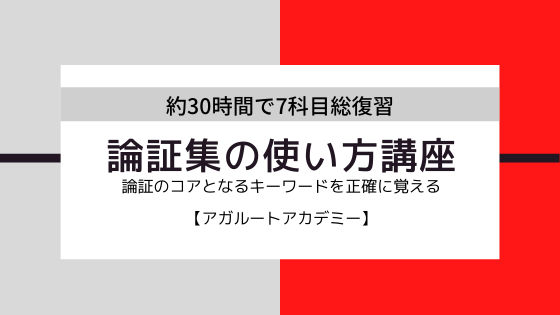
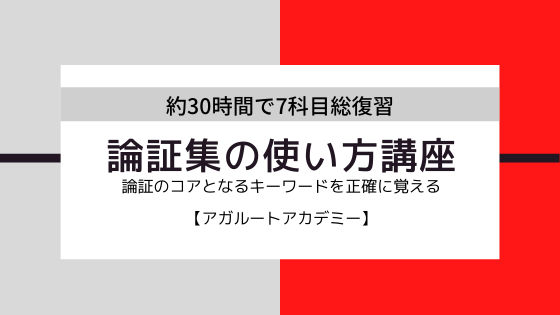










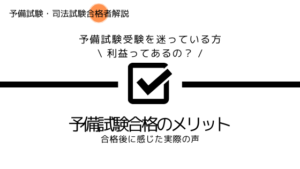
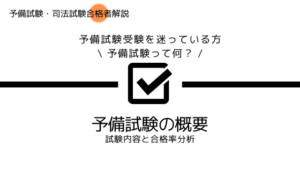
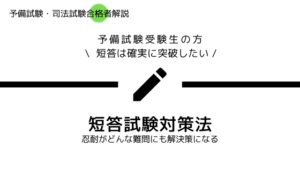

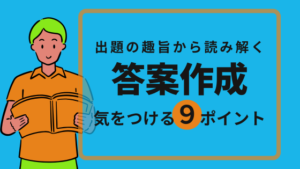
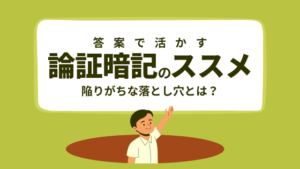
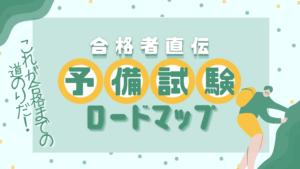




コメント
コメント一覧 (4件)
[…] […]
[…] […]
[…] 【2023年】司法試験予備試験のメリット5選とデメリット4選 […]
[…] 予備試験のメリット、デメリットや予備試験の概要、予備試験の難易度なども解説をしていますので合わせてご確認ください。 […]