令和6年司法試験に不合格だった方へ

本記事は、残念ながら令和6年司法試験に不合格となってしまった方に向けて、令和7年度司法試験合格を目指す戦略をご紹介するものです。
まず、不合格という現実を受け止めることは、大変辛いことかと思います。しかし、本記事を読まれている方は、「何としても来年度は合格を掴みたい」という強い意志を持っていらっしゃることでしょう。当サイトは、皆さんのその思いを応援しています。
本記事では、厳しい言葉や耳が痛い内容も含まれるかもしれませんが、ぜひ、最後までお付き合いください。
お世話になった方々に報告する
まず初めに、辛いかと思いますが、お世話になった方々に不合格を報告しましょう。
合格を期待していた方々に結果を伝えるのは容易ではないでしょう。
しかし、状況を共有することで、今後のアドバイスをもらえたり、相談に乗ってくれる同期やサポートをしてくれる方が見つかるかもしれません。
また、不合格の報告をした後は、「令和7年度司法試験に必ず合格すると宣言する」ことも大切です。
自身の決意を周囲に示すことで、自分に対する励みや支えを得られるはずです。
敗因分析の重要な視点
不合格から学ぶためには、敗因分析が不可欠です。
ここでのポイントは、自己認識に基づく「主観的な敗因分析」と、他者の目を通した「客観的な敗因分析」を行い、「そのずれを確認する」ことです。
- 主観的な敗因分析
- 客観的な敗因分析
- そのずれを確認する
自分の弱点を言語化する(主観的な敗因分析)
主観的な敗因分析とは、自分の内面を掘り下げ、どこに弱点があるかを明確にすることです。
「暗記不足」「当てはめが不十分」など曖昧な理由ではなく、「正確に論証は出来ていたが、考慮要素を理解しておらず、抽出すべき事実が分かっていなかった」「論証を大展開したためにあてはめをする時間的余裕がなく、結果的にバランスが悪くなった」など、できる限り具体的に言語化することで、改善すべきポイントが明確になります。
一定の結論が出たとしても、さらに具体化していってください。これを繰り返し、弱点を細分化していってください。
他者の目で見る(客観的な敗因分析)
次に、他者の目を借りて敗因を分析することが大切です。
信頼できる合格者や司法試験のプロに、自分の答案(できれば再現答案)を見てもらいましょう。他人の客観的な視点からの指摘は、模試だけでは見えない弱点を浮き彫りにしてくれます。
司法試験の再現答案がない方は、過去作成した答案でもかまいません。
合格者の客観的な意見を取り入れることで、主観とのずれに気づき、どこをどう改善すべきかが見えてくるはずです。
主観的敗因分析と客観的敗因分析のずれを認識する
主観的な敗因分析と客観的な敗因分析が完了したら、その違いを確認しましょう。
自分は問題と考えていた点が客観的には改善点であった場合は、要注意です。
そもそも、自分が正しいと思っていた答案の型や論点の理解が根本から間違っている可能性があります。
このステップは非常に重要です。
できれば、信頼できる合格者の仲間に付き合ってもらうとよいでしょう。
敗因分析を実行する
多くの受験生は、再現答案をもとに一度敗因分析を行いますが、重要なのはの敗因分析の後です。
改善策が効果を発揮しているか、常に確認し続けることが肝要です。
長年の癖や弱点は簡単には改善しないため、改善策が効果を生んでいるかを模試や答練を通じて逐次チェックし、不十分であれば新しい方法を試みる必要があります。
また、「仮に答案の分量に大きな課題がある」方であれば、答案の分量が改善しているのか定期的にチェックをするべきでしょう。
短答が苦手なら過去問に挑戦し、得点改善の傾向をチェックするべきです。
せっかく不合格後に時間をとって「敗因分析」をしたにもかかわらず、実行しないと全く意味がありません。
敗因分析を実際の勉強に生かせないと、来年度の司法試験も同じような理由から落ちてしまいかねません。
自分の弱点から逃げない
不合格の原因となった弱点に向き合うのは、精神的に負担が大きいものです。
とくに短答試験や特定科目の得点が低かった場合、その部分の改善は避けたくなるものですが、そこから目を背けずに弱点に向き合いましょう。
例えば、「憲法が大の苦手」という受験生がいいます。
「憲法は捨てて、他の科目で高得点を狙う」という戦略をとろうとする人がいますが、絶対やめてください。
こういう方は、「憲法がFだった人でも合格しているから」とも言います。
しかし、実際に対策をして結果的に「F」になるのと、当初から捨てて「F」を取るのでは話が違います。司法試験の評価は、割り当てる人数が決まっているため、一定基準より下の方は、Fになります。
ぎりぎりFの方と、底なしのFでは全然違います。
そもそも、論文式試験には「足きり点」があります。リアルに底なしのFを取ってしまうと、他の科目がどれだけ良くても不合格です。
捨てて良い科目は司法試験にはありません。
早い段階で苦手分野に取り組むことで、弱点を改善するチャンスが広がります。試験直前期に向けて準備を進めていけば、少しずつ弱点が改善し、本試験では落ち着いて実力を発揮できるようになるはずです。
余談ですが、司法試験は日本最難関の試験です。が、試験は試験です。対策ができるものです。
アカデミックに寄った勉強をして不合格だった方は、「試験対策」を意識してください。つまらない勉強が増えるかもしれません。でも、面白い勉強は、司法試験に合格してから働きだしてからもできます。いまは、「試験対策」のためにつまらない勉強もしてください。
2回目受験生の注意点
令和6年度の試験が初受験だった方は、成績表をもとに、強みと弱みのある科目を明確にしましょう。
しかし注意点として、2回目の受験生は、成績の良かった科目が2年目で急落するリスクがあります。
ある受験者も、初年度に良かった公法系が2年目で点数が大幅に低下した経験があるように、前年度の実力を維持するためには、すべての科目に均等に時間をかけることが必要です。
特に年明けからは、すべての科目に意識的に時間を配分し、実力を維持することを意識しましょう。
過去問から逃げない
過去問を解くことは、合格に向けた自己分析の大切な一環です。
過去問を通じて自分の実力を試すと、苦手分野や改善が必要なポイントが明確になります。
過去問演習で思うような得点が取れないと、精神的に負担がかかるかもしれませんが、これはあくまで練習の場であり、そこでの失敗は本試験への貴重な改善材料となります。
また、過去問に取り組むことで、その年の出題傾向や頻出テーマを把握でき、実戦で求められる解答技術が身につきます。過去問を通じて苦手分野を知り、そこを重点的に復習することで、着実に力を付けていけます。
さらに、過去問に取り組んでおくことで、翌年の対策が必要になった際にも、自己分析の記録が残り、次回の学習計画を立てやすくなります。
勉強計画を確定する
敗因分析が終わり、自分の弱点が明確になったら、次は計画を立てましょう。
残りの8か月は、まさに「人生最大の努力」を注ぐときです。
達成可能な目標を立て、毎日、日々の進捗を確認しながら進めていきましょう。
自己の改善策に集中する時間を確保することで、リベンジ合格に大きく近づくはずです。
予備校の講座に新しく取り組むのはありか?
当サイトとしては、フルカリキュラムは勧めませんが、弱点の内容に応じて、単品の講座を受講するのはありだと思います。
例えば、法的三段論法のうち「規範定立」に大きな課題があるのであれば、「論証集の使い方講座」を導入するのはありだと思います。
参考:【2024年】アガルート『論証集』の究極の使い方と評判
また、判例の理解が不十分で独学では厳しいと考えるのであれば「判例解説の講座」を取り入れるのも良いかと思います。
しかし、予備校の講座を導入する場合は、敗因分析を踏まえて、
「その講座が本当に必要なのか」
「その講座を購入すれば弱点を克服できるのか」
「司法試験合格に寄与するのか」
を慎重に検討してください。
私が挫折から司法試験合格まで至ったストーリーはこちらからご確認頂けます。
興味がある方は、読んでみてください。
最後に
司法試験の合格を勝ち取るためには、敗因分析をしっかりと行い、計画を練って、弱点を克服し続けることが大切です。
繰り返しになりますが、敗因分析は、主観と客観の両面から行い、その差を認識してください。
自分の評価と他社の評価の差を理解できれば、正しい方向で勉強を進めることができます。
また、不合格の事実に直面し、お辛い状況だと思います。
しかし、1年や2年の差は本当に弁護士になれば分かりますが、誤差です。
5年、10年かかったとしても、最終的に合格された先輩方は、その過去を活かして充実した弁護士生活を送っています。司法修習にいけば、旧司法試験のリベンジ組の方も結構いらっしゃいます。
司法試験に受かってしまえば、人生なんとかなります。残りの8か月は、人生で一番頑張ったと言い切れるように必死に勉強しましょう。
本当の最後に、皆さんは、日本最難関試験にチャレンジしています。このこと自体が、偉大なことです。どうしても法曹になりたい理由があるからこそ、最難関試験に挑戦されている。自分を褒めたたえてください。
私は、凡人の法学部生でしたが、運よく司法試験に合格することができました。皆さんであれば、必ず合格することができます。
\売り切りセール10%OFF/


| 【アガルート】売り切りセール | |
| 期間 | 2024年10月24日(木)~2024年12月16日(月)23:59 まで |
| セール対象 | 【2025・2026年合格目標】予備試験最短合格カリキュラム 【2025・2026年合格目標】予備試験最短合格カリキュラム ライト |
| 受講特典 | 司法試験講座が30%値引きも! |
フルカリキュラムをお得に始めるチャンス















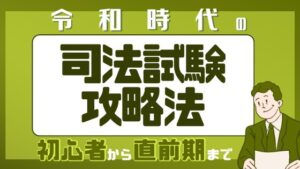
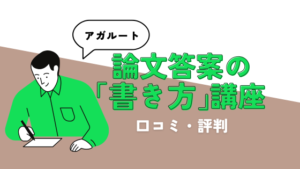




コメント