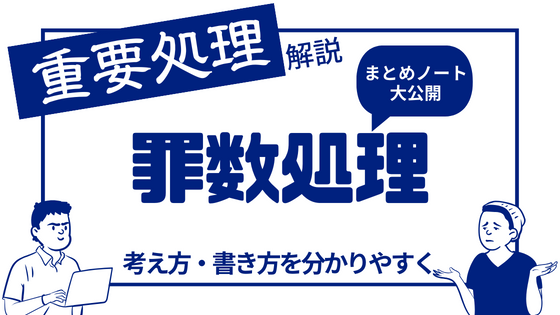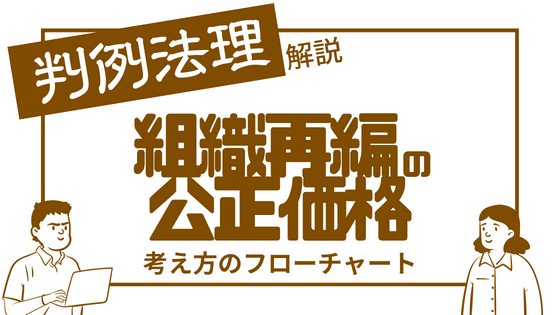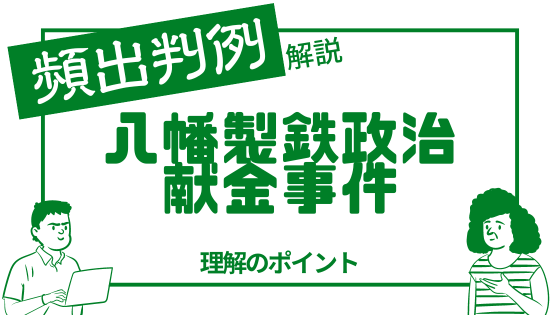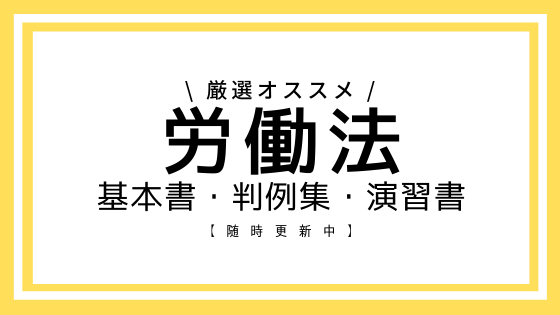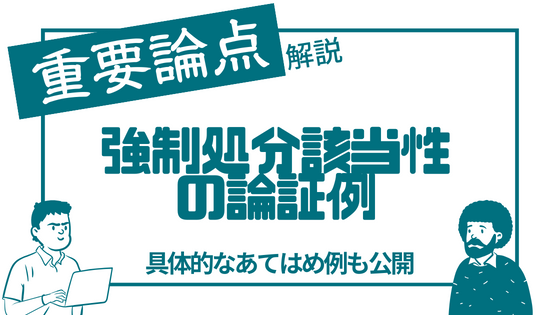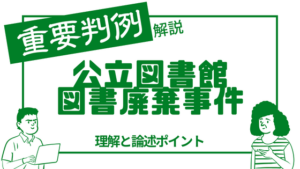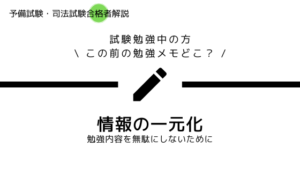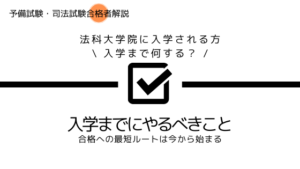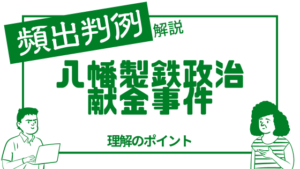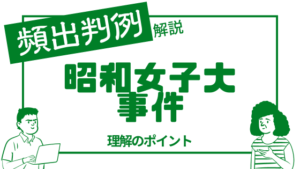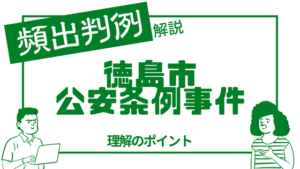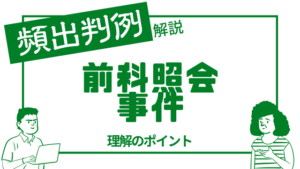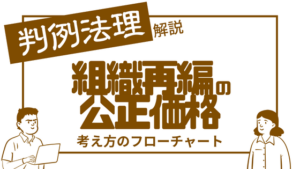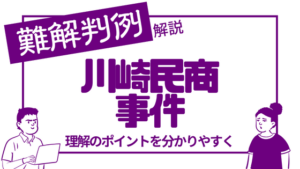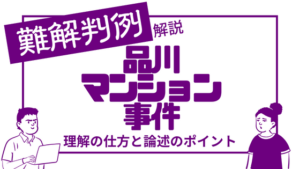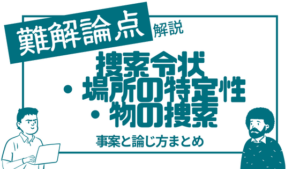【憲法判例】公立図書館の図書廃棄事件(最高裁平成17年7月14日)の理解のポイント論述の仕方

「公立図書館の図書廃棄事件(最高裁平成17年7月14日)の論述例が知りたい
「三者間形式ではどのように主張を整理できるのか」
今回は、憲法の重要判例である公立図書館の図書廃棄事件(最高裁平成17年7月14日判決)を題材にした、論述例をご紹介したいと思います。船橋市西図書館蔵書破棄事件と言われているものです。
※司法試験受験前に作成したまとめノートから抜粋したものであって、内容の正確性を保証するものではありません。一つの論述例として参考にしてください。ご利用は、自己責任でお願いします。
表現の自由に関する重要判例の一つですね!
近年の司法試験では、三者間形式の論述は求められていないですが、三者間形式で主張を整理する場合、どのような立論があり得るのかはストックしておくとよいでしょう!
公立図書館の図書廃棄事件「原告の主張」例
1. 憲法上の権利の保障と制約
著作者にとって自らの著書が公立図書館において閲覧に供された場合において、公立図書館において閲覧に供されることで、自らの見解を伝達するという権利利益は、憲法21条が保障する表現の自由として保障される。本件では、図書館員が自らの価値観に基づいて図書を廃棄していることから、上記利益を制約している。
2. 合憲性判断基準
憲法21条の規定する表現の自由には、個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的な価値(自己実現の価値)、言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという民主政に資する社会的な価値(自己統治の価値)を併せ持つものであり、基本的人権の中で特に尊重されるべき権利である。
さらに、本件において、図書館員は、自己の価値観に基づき図書を廃棄しており、これは表現物の内容に着目した処分であり、恣意的濫用的処分と言える。
よって、本件廃棄処分は、処分目的がやむにやまれぬ公共の利益の保護にあり、目的達成手段が目的実現にとって必要不可欠である場合に限り、当該処分は合憲であると解すべきである(厳格な基準)。
(割愛)
公立図書館の図書廃棄事「被告の反論」例
1. 憲法上の権利の保障ついて
原告の主張する利益は、公立図書館に対して自己の見解を表現する場所として使用させることを求めるものと解されるところ、表現の自由は「国家からの自由」を核心とする自由権であり、国家による積極的行為を要求しうる権利ではないから、原告が主張する利益は、表現の自由として保障されない。
2. 合憲性判断基準
仮に原告の主張する権利利益が表現の自由として保障されるとしても、公立図書館は図書について管理権を有する。合憲性判断基準としては、表現の自由と管理権保護の調和が図られるものであるべきであり、厳格な基準は妥当でない。
公立図書館の図書廃棄事件「私見」例
1. 憲法上の権利の保障と制約
確かに、表現の自由は自由権であるから、国民は、思想情報を表現するために必要な特定の施策を請求しうる権利を当然に持つものではない。それゆえに、公立図書館はいかなる図書を購入し閲覧に供するかについて広い裁量を有するから、原告の主張する権利利益は、公立図書館が裁量に基づき当該図書を購入して公衆の閲覧に供したことによって反射的に生じる事実上の利益に過ぎないとも考えうる [1]。
しかし、図書の購入と異なり、閲覧に供した図書の管理については、公立図書館に広範な裁量を認めるべきではない。なぜならば、公立図書館が図書を購入しそれを公衆の閲覧に供したことにより、当該図書の著作者にとっては、公立図書館において閲覧に供されることで、自己の見解を伝達することができるというのが、その者にとってのベースラインとなるため、後になって当該図書を非公開や廃棄にすることは、当該図書の著作者の表現行為を妨害するという性格を帯びるからである [2]。
したがって、原告の主張する利益は、表現の自由として保障されていると解すべきである。
2. 合憲性判断基準
確かに被告の主張の通り、公立図書館には図書について管理権が認められる。しかし、①一般公衆が自由に出入りできる場所であり、かつ、②表現のための場として役に立つのであれば、その場所はパブリックフォーラムとして、その場所における表現の自由の保障は可能な限り配慮されるべきである。なぜならば、表現の自由の行使には、表現のための物理的な場所が必要であるところ、①及び②の要件を満たす場所については、表現をするための場所として確保されるべきだからである。本件において公立図書館は、会館時間であれば一般公衆が自由に出入りできる場所であり、かつ、公立図書館は著作者の見解をより多くの人に知ってもらうために役立つ場所であることから、パブリックフォーラムにあたる。
よって、原告主張のとおり、厳格な基準によって合憲性を判断するのが妥当である。
[1]第一審及び原判決は、原告の主張する権利利益は、反射的に生じる事実上のものに過ぎないとしている。
最後に
いかがでしたでしょうか?この記事が皆様のお役に立てば幸いです。
この記事を読んだ方は以下の記事も読んでおります。