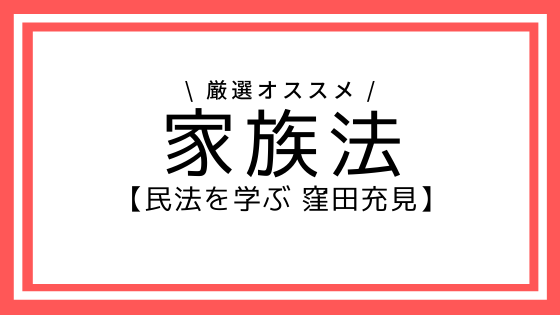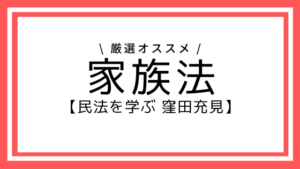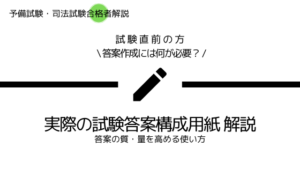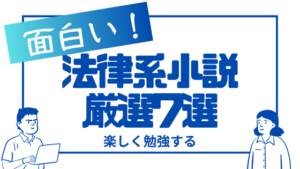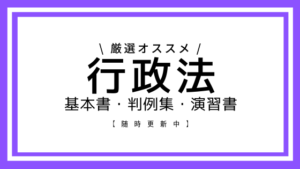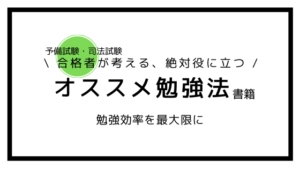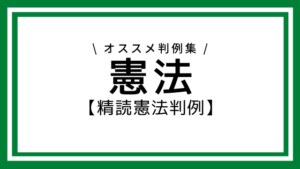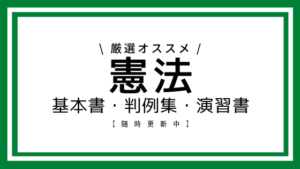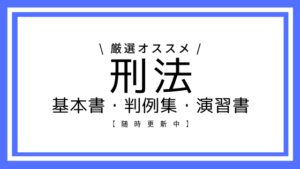今回は、『家族法 民法を学ぶ(窪田充見)』のレビュー記事です。
この記事はこんな方におすすめ
・ 『家族法 民法を学ぶ』のレビューが気になる
・ 家族法のおすすめの基本書を知りたい
・ 司法試験、予備合格者の使用教材が気になる
まずは、家族法の学習の必要性から解説します。
家族法の学習の必要性
家族法分野で、基本書の購入を検討している方は少ないかもしれません。なぜなら、論文試験で出題される可能性が低いと考えている方が多いからです。
しかしながら、近年の司法試験を分析してみると、かなりの頻度で家族法の理解が問われています。特に平成30年度の司法試験では、遺言が設問の一つとして、出題されました。
家族法分野を学習してこなかった方には難しい出題になったと思います。このように、家族法分野の学習の必要性は高まってきています
それでは本書の書評に移ります。
『家族法 民法を学ぶ』の書評
本書は以下のような点で、人気が出ていると考えます。
丁寧かつ具体的な説明
本書の特徴としては、初学者がつまずきやすい箇所について、かなり丁寧かつ具体的に解説が施されている点が挙げられます。 基本的な親族法・相続法の規律について、かなり詳しく書かれています。
コラムが充実
コラムでは、論文対策として不要だけど、教養として知っておくべき知識や、最新の学説の動向にも言及されています。
近年の判例もフォロー
また、家族法分野では、近年重要判例が登場してきていますが、第3版に収録されている最も新しい判例は、最高裁平成28年12月19日であり、近年の判例もフォローされています。 他方で、かなり丁寧な説明に加えて、具体例も豊富に掲載されているため、やや分量が多いです。ページ数で言えば、607ページあります。家族法分野の教科書としては、分厚い方だと思います。 もっとも、本書は通読するのに適していると思います(通読するべき基本書です)。 個人的には、家族法分野の基本書として、まず第一に読むべき基本書だと思います。 理由は、繰り返しになりますが、非常にわかりやすいからです。
非常に分かりやすく読みやすい
家族法分野は、条文だけを追いかけていてもよくわからないものがあります。このような条文に遭遇した際に、自己流解釈等をしてしまう可能性があります。 本書では、学生が誤解しないように、非常に分かりやすい解説がされています。 そのため、家族法の初めの一冊に選ぶべきです。かなりおすすめです。
窪田教授の文章は、読者を惹きつける
また、本書の文体は、口語体が使われている部分が多いため(特にテーマごとの導入部分)、窪田教授の授業を聞いているような感覚を味わうことができます。
この点が、本書の一番の魅力かもしれません。その読みやすさ、面白さから窪田教授のファンになる人も多いと思います。わたしも、本書での学習にハマったため、特に必要ではなかった窪田教授が書かれている『不法行為法 — 民法を学ぶ 第2版』も購入してしまいました。
それくらい、窪田教授の文章には、読者を惹きつけるものがあります。 したがって、一気読みが可能です。気づいたらこんな時間になってしまっていたとか、そういう体験も基本書ですることが出来ます。
ぜひ窪田教授には、他の分野の基本書も執筆してもらいたいですね。本当に、切に願っています。
以上、家族法オススメの基本書『家族法 民法を学ぶ』(窪田充見)の書評記事でした。
まとめ
近年の司法試験では、家族法の分野の問題も出ています。是非、家族法の基本書である『家族法 民法を学ぶ(窪田充見)』を使用して学習を進めてみてください。