岐阜県青少年保護育成条例事件(最判平元.9.19)をどこよりも分かりやすく解説
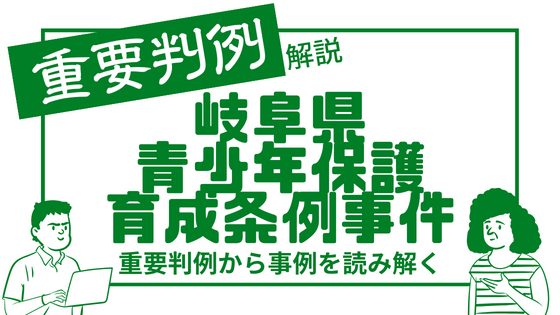
『岐阜県青少年保護育成条例事件の概要は?』
『岐阜県青少年保護育成条例事件のポイントは?』
『岐阜県青少年保護育成条例をさらに理解するためには?』
岐阜県青少年保護育成条例は、青少年には不適切と思われる性的な表現のある写真集などについて、有害図書に指定したうえで、自動販売機での販売を禁止する条例でした。
この条例の規定が、憲法21条1項で保障されている表現の自由と2項の検閲の禁止に抵触しないのかが問題となった判例です。
結論から言うと、最高裁は、岐阜県青少年保護育成条例の規定は、憲法21条1項で保障されている表現の自由を侵害するものではないし、検閲にも当たらないとの判決を下しています。
司法試験予備試験応援サイトでは、泉佐野市民会館事件判決や夫婦同性合憲判決事件などの判例解説記事を公開していますので合わせてご参照ください。
岐阜県青少年保護育成条例事件の概要
当時、PTAが悪書追放運動を行っており、この影響を受けて、ほとんどの都道府県で青少年保護育成条例が制定され、性的な表現のある写真集などについて青少年への販売を規制する「有害図書規制」が導入されていました。
岐阜県青少年保護育成条例もその一つですが、次のような規定が設けられていました。
- 知事は、著しく性的感情を刺激し、又は著しく残忍性を助長するため、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認める図書について、岐阜県青少年保護育成審議会の意見を聴いたうえで、有害図書に指定できる。
- ただ、有害図書のうち、「特に卑わいな姿態若しくは性行為を被写体とした写真又はこれらの写真を掲載する紙面が編集紙面の過半を占めると認められる刊行物」は、岐阜県青少年保護育成審議会の意見を聴かなくても、あらかじめ規則で定めるところにより包括的に有害図書に指定できる。
- 有害図書に指定されると、有害図書を青少年へ販売、配付、貸し付けすることが禁止される共に、自動販売機で販売することも禁止される。違反した場合は罰則が科される。
この条例に基づいて、岐阜県知事が有害図書を指定しました。
ところが、自動販売機で図書を販売していた会社が指定された有害図書を自動販売機で販売したために、会社の代表取締役Xが条例違反により起訴されて有罪となりました。
これに対して、Xが条例の規定、とりわけ、包括指定方式や自動販売機での販売を禁止する規定が憲法21条に違反するのではないかとのことで上告した事件です。
岐阜県青少年保護育成条例事件の最高裁の考え方
最高裁が具体的にどのように判断したのか確認していきましょう。
憲法21条1項の表現の自由に関して
憲法21条1項の表現の自由には、情報を受領し、情報にアクセスする権利も含まれています。
この点は、最高裁も未決拘禁者新聞閲覧制限事件(よど号ハイジャック記事抹消事件)で認めています。(最大判昭和58年6月22日)
写真集などを有害図書に指定して、青少年への閲覧を制限することは、青少年の閲覧の自由への制約になります。そのため、憲法21条1項に反するのではないかが問題になるわけです。
この点、最高裁は次のように述べました。
よって、「有害図書の自動販売機への収納の禁止は、青少年に対する関係において、憲法21条1項に違反しない」と判断しました。
また、有害図書の自動販売機への収納を禁止することは、成人の閲覧の自由への制約にもなるのではないかという問題があります。
最高裁はこの点についても、「青少年の健全な育成を阻害する有害環境を浄化するための規制に伴う必要やむをえない制約である」として、憲法21条1項に違反しないとの見解を示しました。
憲法21条2項の検閲の禁止に抵触しないのか?
都道府県知事が写真集などを、あらかじめ規則により包括的に有害図書に指定して、販売を制約することは、検閲に当たるのではないかが問題になります。
この点は、最高裁は、過去の最高裁判例を引用して、「検閲に当たらないことは、当裁判所の大法廷判例の趣旨に徴し明らかである」と述べているだけです。
引用したのは、税関検査訴訟の判例です。(最大判昭和59年12月12日)
検閲の定義について示した判例として知られています。
具体的には、
これによって、不適当と認めるものの発表を禁止することを指す。と定義しました。
岐阜県青少年保護育成条例に当てはめると、知事が主体となって行うもので、写真集などの表現物を対象としているので、1、2の要件には当てはまっていますが、既に発売されたものを対象とするため、3、4の要件には当てはまりません。
伊藤正己裁判官も補足意見の中で、「すでに発表された図書を対象とするものであり、かりに指定をうけても、青少年はともかく、成人はこれを入手する途が開かれているのであるから、「検閲」に当たるということはできない。」と述べています。
パターナリズムに基づく制約とは
この判例では、伊藤正己裁判官が補足意見の中で、青少年の知る自由はパターナリズムに基づく制約を受けることに言及している点も注目しておくべきでしょう。
要約すると次のように述べています。
青少年は、人格を形成していく大事な時期に当たるため、幅広い知識や情報に触れることで精神的に成長する必要があります。そのため、青少年の知る自由の保障が重要になるわけですが、成人と比べるとその保障の程度は低くなるとしています。
なぜなら、青少年は成人と違って、情報を選別する能力が未熟なため、自分で知識を選ぶという前提が成り立ちません。そのため、青少年の知る自由は一定の制約を受けるべきであり、青少年の精神的未熟さから生じる害悪から守られる必要があるわけです。このような考え方をパターナリズムに基づく制約と言います。
そして、ある表現が青少年に向けられる場合には、成人に対する表現の規制の場合のように、その制約の憲法適合性については、厳格な基準が適用されず、違憲判断の基準についても成人の場合とは異なり、多少とも緩和した形で適用されるとしています。
このような考え方で、岐阜県青少年保護育成条例についてみると、青少年が有害図書に接することで、「非行を生ずる明白かつ現在の危険がある」とは言えないし、科学的にその関係が論証されているとは言い難いものの、青少年保護のための有害図書の規制が合憲であるためには、青少年非行などの害悪を生ずる「相当の蓋然性があることで足りる」と解してよいと言うことです。
青少年保護条例をめぐるその後の判例の動向
青少年保護条例により、有害図書類の「自動販売機」への収納を禁止し、その違反に対し罰則を科すことは違憲ではないかと言う点はその後もたびたび争われました。
福島県青少年健全育成条例違反被告事件(最判平成21年3月9日)も有名判例の一つなので合わせて押さえておきましょう。
この事件でも、福島県知事が有害図書に指定した図書を、自販機で販売していた会社が起訴されました。
ただ、自販機が置かれた店内には監視カメラが設けられていて、監視員が監視センターに設置されたモニターで来店者を確認できる仕組みになっていました。
来店者が明らかに成人であれば、販売可能な状態にしますが、年齢に疑問がある場合は身分証明書の提示を求めて、来店者が18歳未満ではないことを確認できた場合のみ、販売できるようにしていました。
そのため、自販機で販売しているにしても実質、対面販売と変わりはないと主張して争いました。
しかし、監視センターのモニター画面では,必ずしも客の容ぼう等を正確に判定できるわけではない上,客が立て込んだ時などには18歳未満かどうか判定が困難な場合でも購入できる状態になっていたとの事実認定に基づいて、最高裁は、対面販売の実質を有しているとは言えず、「自動販売機」に該当することは明らかだとしました。
また、憲法21条関係についても、有害図書類の「自動販売機」への収納を禁止することは、
1.青少年以外の者に対する関係において、有害図書類の流通を幾分制約することになるが、書店等における販売等は自由にできる。
2.青少年健全育成条例による規制は、青少年の健全な育成を阻害する有害な環境を浄化するための必要やむを得ないものである。
よって、憲法21条等に違反するものではない。との判決を下しました。
憲法答案の書き方には作法がある?
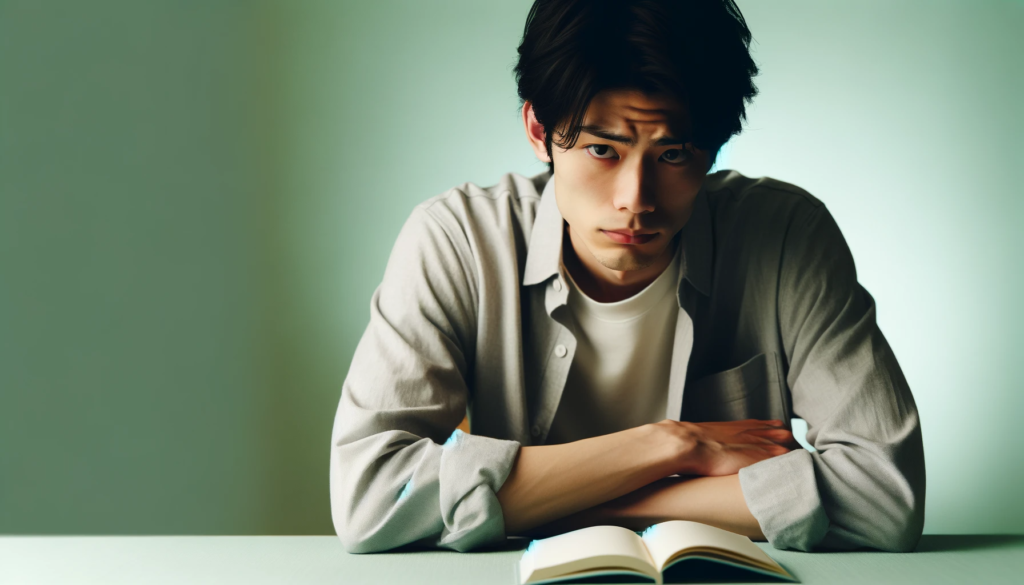
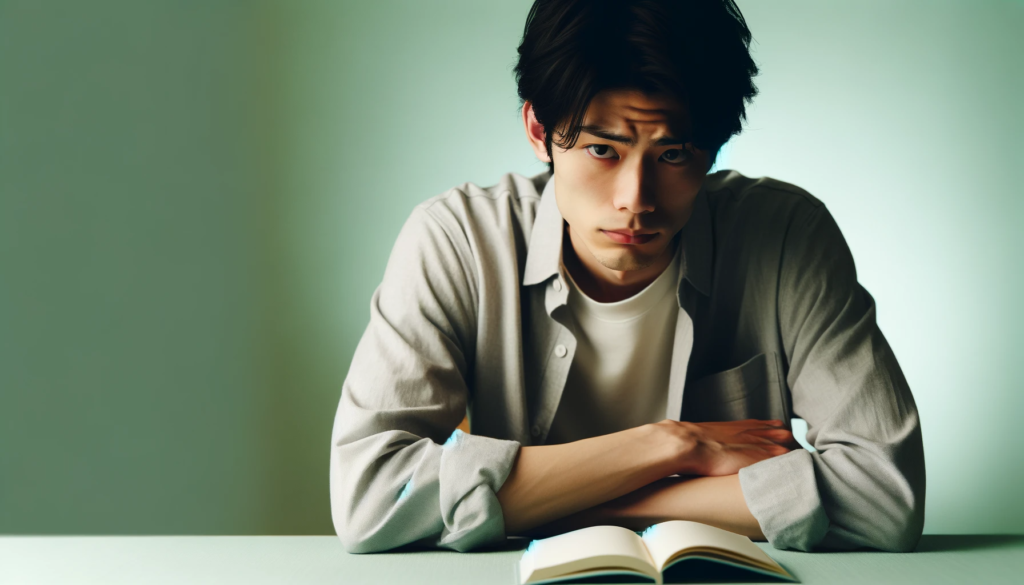
憲法はほかの科目よりも憲法答案の型が重要です。
理解した知識をどのような答案上で表現するのか、が重要です。
判例知識をインプットすることも大切ですが、その前に憲法答案の型を理解しておくとより効率的なインプットができるでしょう。
憲法答案の型について勉強したい方は「司法試験憲法の勉強法-答案の型から直前期の勉強まで徹底解説」をご確認ください。










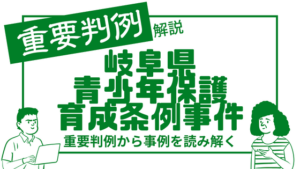


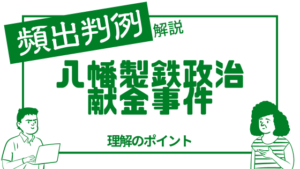
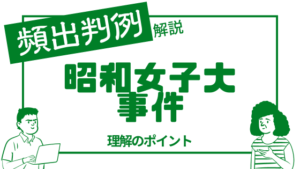
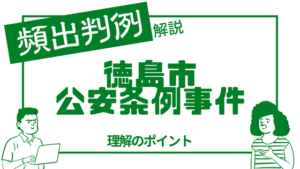
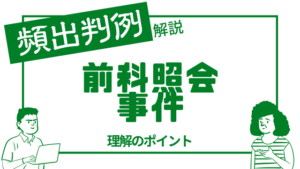
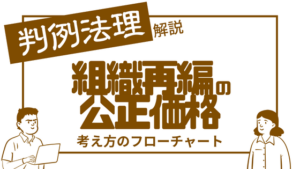
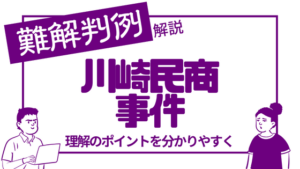
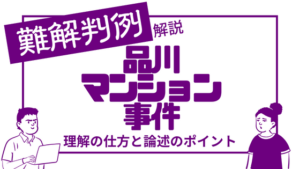
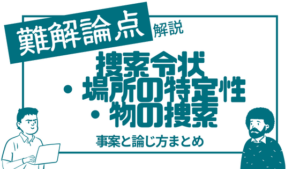

コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 司法試験予備試験応援サイトでは、岐阜県青少年保護育成条例事件や徳島市公安条例事件などの重要判例の解説記事を公開しています。合わせてご確認ください。 […]
[…] 当サイトでは、これまで憲法の重要判例解説として「徳島市公安条例事件」「謝罪広告事件」「岐阜県青少年保護育成事件」等の解説記事を公開しています。 […]