法学既習者に総合講義100が断然オススメである理由【アガルート】
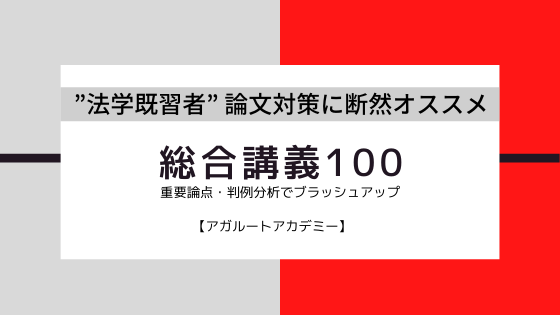
私は、総合講義100を一元化教材として予備試験に最終合格し、翌年の令和元年司法試験に論文総合130位代で合格することが出来ました。
今回は、総合講義100の授業を試験直前期まで聞き直し、テキストを司法試験の論文最終日まで使い倒した私が、本講座の魅力をお伝えしたいと思います。
アガルートアカデミーは、本ブログイチオシの司法試験予備校です。アガルートアカデミーが提供しているそのほかの講座のことが知りたい方は、サイト上部の「アガルート」をクリックしてください。アガルート関係の記事を読むことが出来ます。
1. 工藤北斗講師の授業
講座選びで一番のポイントは、どこの予備校の講座なのかではなく、講師が誰なのかです。どれだけクオリティーの高いテキストが用意されていても、誰が教えるかで、講義全体のクオリティは大きく左右されます。司法試験予備校の選び方については、司法試験予備校の比較記事でも解説しています。
講座選択の際には、その企画内容で決めるのではなく、講師が誰なのか確認しましょう。
総合講義100は、工藤北斗講師が全科目を担当されています。工藤北斗講師の授業は一言で言えば、正確で分かりやすい授業です。現在、予備校業界は、群雄割拠の世界であり、珍しい経歴を持つ講師、司法試験に超上位合格をしている講師など英雄がたくさんいます。
その中でも、王道をひた走っているのが、工藤北斗講師だと思います。飛び道具などは一切使わず、受講者が効率よく無駄なく学習できるように、正確でわかりやすい解説を極めている先生です。
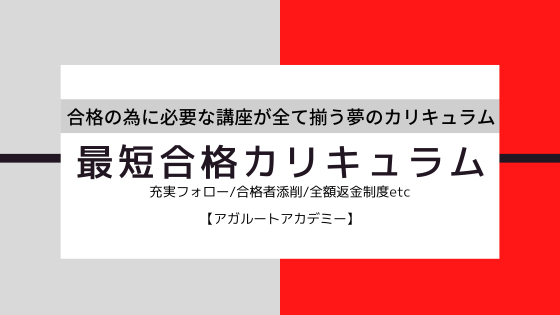
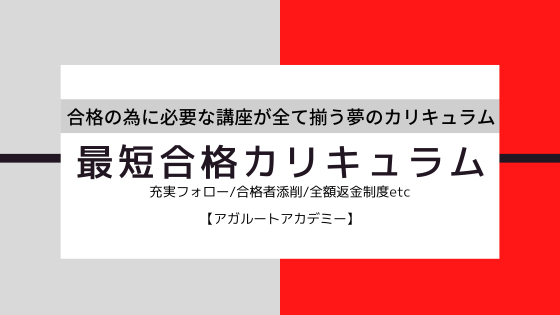
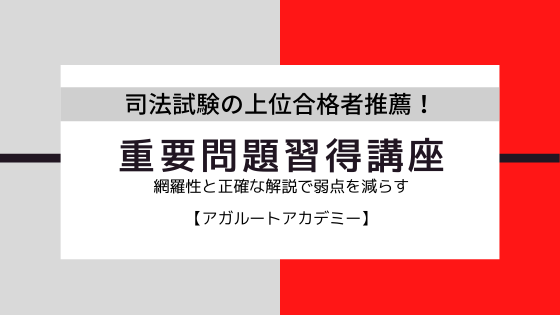
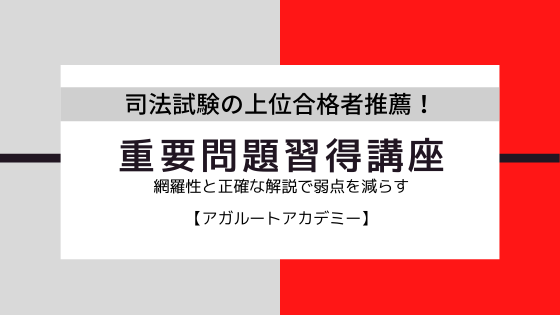


2. 100 時間で7科目を網羅できる
まず、前提として、アガルートの司法試験対策講座としては、初学者を対象とした教材として総合講義300があります。そのため、法律初学者は、必ず総合講義300から受講を始めてください。総合講義100は、法律初学者には難し過ぎます。この点、ご注意ください。
本講座は、約100時間で7科目を網羅することが出来るように設計されています。
2019年度版の各科目の講義時間は以下の通りです。
◇憲法:約18時間
◇行政法:約11時間
◇民法:約20時間
◇商法:約10時間
◇民事訴訟法:約12時間
◇刑法:約16時間
◇刑事訴訟法:約13時間
◆合計:約100時間
※ 時間数は,多少前後する場合がございます。(公式サイトより引用)
気合いだせば、一週間で7科目一周できます。笑
(講義の公開時期は科目ごとにばらつきがあるので、全科目が公開されてからという条件付きではありますが)
3. 論文対策に特化した講義
本講座は、法律既習者を対象としています。そのため、論文対策には必ずしも必要はないけど、基本の理解としては必要なテーマ、例えば、民法の私的自治の原則など、基本的な事項に関する解説は、省略または簡潔な解説にとどめてあります。
論文対策上重要な事項(判例や論点の解説)に重点が置かれた講座であると感じました。
私の場合、法学部に在籍にしており、一通り大学の授業で学習していたので、綜合講義100を受講することに決めました。受講した感想としては、思ったよりハイレベルだということです。論点がマイナーなわけではなく、重要論点・判例の分析が秀逸です。ロースクール生でも難しいと感じる部分もあると思います。
司法試験は、最難関試験の一つです。実際に、出題される問題は、非常に難解です。出題の趣旨通りの回答ができるのは、ごく限られた超上位合格者だけです。逆に言えば、司法試験委員会が求めるレベルの論述ができなくても、合格することは可能です。司法試験委員会が求めるレベルが100だとすると、80とか70のレベルの論述が出来れば十分に合格できます。
ここまで説明すると、「80とか70レベルのことを勉強したらいいや」と思う方もいるかもしれません。しかし、試験本番で80とか70のレベルの論述をするためには、普段の勉強では100のレベルで勉強しておく必要があります。普段から高度なインプットをしているからこそ、本番で70とか80の水準の論述が出来ます。
4. 音声データのダウンロード
音声データをダウンロード出来るので、ネット環境のない場所でも学習することが出来ます。めちゃ便利です。視聴期限も気にせず学習できます。
私の場合は、音声をiphoneに取り込んで、再生スピードを変更することができるアプリを使って、1.5倍速くらいで聴いていました。寝る前に、スリープタイマーをセットして、15分くらい聞くこともありましたし、通学時間に聞くこともありました。
5. テキストがハイクオリティー
冒頭で、講座選択の際は、誰が講師なのかが一番重要と言いましたが、二番目にチェックすべき点は、どんなテキストなのかです。
特に、基礎(インプット)講座は、司法試験の最終日まで使えるテキストかどうかという視点から選ぶべきだと思います。これから情報を一元化していき、最後の見直し教材に仕上げていくイメージが出来るのか。受講を決意する前に想像してみてください。
「分厚すぎて最後まで使うイメーシが湧かない」
「なんだか愛着が湧かない気がする」
と思うならそのテキストを使う講座はおすすめできません。
この点、総合講義100のテキスト(総合講義300と同一のもの)は、最後の最後まで使い続けるイメージができます。
まず、①本テキストは、論文対策に特化したテキストです
よく、短答知識も全て集約されている予備校テキストもありますが、個人的には、短答プロパーの知識は、短答の勉強として分けてやる方が効率的です。
本テキストは、論文対策に特化しているため、何が論文対策として重要なのかがわかります。
決して分厚いテキストでありませんが、合格に必要な知識や思考法が詰まっています。最新の学説状況も反映されています。
次に、②本テキストは、フルカラーです。白黒よりフルカラーの方が、絶対良いです。見栄えの良いテキストの方が、やる気出ますよ。笑 非常に単純な理由ですが、司法試験の勉強は、長期戦ですから、大切なことです。


③紙質が良いです。司法試験まで使うことを考えると紙質は良いものを選ぶべきです。ロースクール入試の際に、ボロボロの某塾のテキストと使っている人を見かけたことがあります。おそらく、司法試験までに違う教材に乗り換えたんじゃないかなと思っています。ある程度、耐久力のあるテキストを選ぶことも大切だと思います。
総合講義のテキストは、フルカラー仕様のためか、光沢があり、比較的良い紙が使われているように思います。
④余白があり、一元化しやすい。本テキストには、書き込みが出来る余白が用意されているので、一元化教材として仕上げていくことが出来ます。基礎講座のテキストは、一元化教材になるべきテキストなので、一元化しやすい作りになっているかは、要チェックポイントです。


私は、写真のように本テキストを使っていました。これ直前期の使用状態なんですが、
・書き込みがしやすいように裁断化
・ファイルが邪魔に感じたので、ファイルからカードリングに変更
・検索しやすいようにインデックス化
・直前に見直したい箇所には、赤付箋
など色々工夫していました。
カードリングでファイルするのはおすすめしません。笑
負荷が二つの穴に集中するので、さすがのアガルートのテキストでもボロボロになって、直前期に補強シールを貼りまくる羽目になったので笑
最後に、⑤過去問出題マーク等学習の便宜が図られている。過去問出題マークなどが、当該判例・論点ごとに記載されているので、学習がしやすいです。
また、重要問題習得講座や、論証集講座とのテキスト間の相互参照が出来るように、該当問題数・ページ数が掲載されています。
以上のように、総合講義のテキストは、ハイクオリティーです。私も、司法試験の論文式試験最終日まで、使用していました。 というか、試験が終わった今でも使っています。
最後に
今回は、総合講義100の魅力をお伝えさせて頂きました。個人的には非常におすすめの講座ではありますが、最終的に受講を決意するのは貴方です。受講相談や無料講義の視聴などをして、ご自身でよく考えてから受講すべきか考えてください。










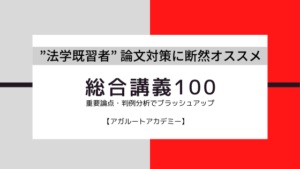
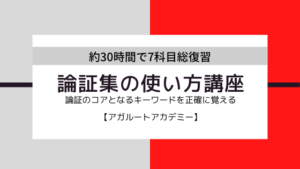
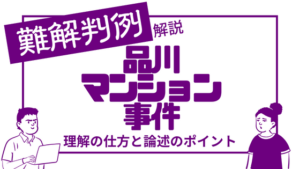
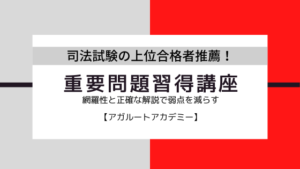
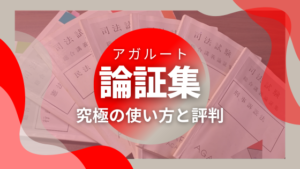

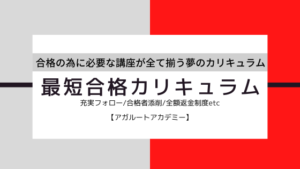
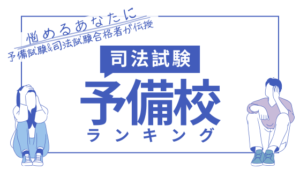

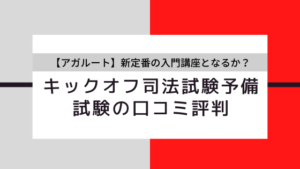


コメント
コメント一覧 (13件)
[…] 法学既習者に総合講義100が断然オススメである理由【アガルート】 […]
[…] […]
[…] 202… あわせて読みたい 法学既習者に総合講義100が断然オススメである理由【アガルート】 […]
[…] 法学既習者に総合講義100が断然オススメである理由【アガルート】 […]
[…] あわせて読みたい 法学既習者に総合講義100が断然オススメである理由【アガルート】 […]
[…] […]
[…] 今回は、私が、アガルートア… あわせて読みたい 法学既習者に総合講義100が断然オススメである理由【アガルート】 […]
[…] 初めから深堀学習を含んだ講座を受講したい方はアガルートの総合講義がおすすめです。 […]
[…] 法学既習者に総合講義100が断然オススメである理由【アガルート】 […]
[…] 法学既習者に総合講義100が断然オススメである理由【アガルート】 […]
[…] 法学既習者に総合講義100が断然オススメである理由【アガルート】 […]
[…] あわせて読みたい 法学既習者に総合講義100が断然オススメである理由【アガルート】 […]
[…] ・【2024年】アガルート『論証集』を使った身になる勉強法と合格者の使い方・法学既習者に総合講義100が断然オススメである理由【アガルート】・【予備合格者解説】アガルート 『論証集の使い方講座」の使い方を徹底解説・【合格者解説】総合講義100の評判と使い方-使い方次第でもっと合格に近づく・上位合格者によるアガルートの短答知識完成講座のレビューと使い方・【2024】アガルートの重要問題習得講座の使い方と評判【上位合格者解説】 […]